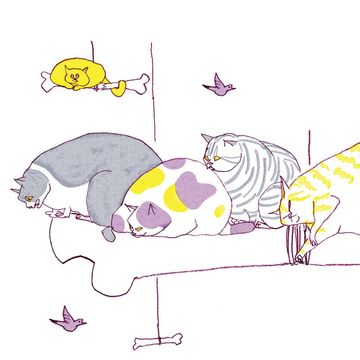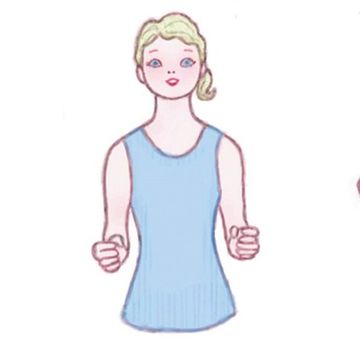氷に覆われた大陸、南極。かつてマイナス89.2℃という、史上最低気温を記録したこともある極寒の地は、昨今では一般人も行くことができる新たな観光スポットとして注目を集めています。
フランスのクルーズ会社、ポナンが実施する最新鋭の砕氷船 (さいひょうせん)によるクルーズもそうした旅のひとつ。南極の短い夏が終わろうとする3月、シーズン最後のクルーズが実施されました。
地球温暖化の影響を受け、氷が解け始めているとされる大陸で懸命に生きるペンギンやオットセイ、人間の存在を拒むかのような峻烈な光景……。エベレスト山頂をはじめ、世界中の極地・僻地での撮影を経験してきた、写真家の上田優紀さんによる写真とともに、2週間の船旅をリポートします。
・・・
■この続きは有料会員にご登録の方は、ハーストIDでログインするとお読みいただけます
● 面積は日本の36倍。分厚い氷に覆われた広大な大陸
● 人間を恐れず気ままに歩くジェンツーペンギン
● つぶらな瞳で見つめてくるオットセイの子ども
● 環境負荷を最大限減少させた最新鋭のクルーズ船
● 戻る場所のある動物たち。では人間の戻る場所は……(残り5582文字)
目次
1.面積は日本の36倍。分厚い氷に覆われた広大な大陸
2.人間を恐れず気ままに歩くジェンツーペンギン
3.つぶらな瞳で見つめてくるオットセイの子ども
4.環境負荷を最大限減少させた最新鋭のクルーズ船
5.戻る場所のある動物たち。では人間の戻る場所は……
1.面積は日本の36倍。分厚い氷に覆われた広大な大陸
南米大陸の南端の港町、アルゼンチン領ウシュアイアを出港して3日目の明け方、白み始めた気配に船室のカーテンを開けると、夜明けの海に青白く光る塊が浮かんでいた。
バルコニーに出る。ウシュアイアまでの経由地、チリの首都サンティアゴでの30℃を超す気温と打って変わり、寒い。塊はひとつではなく、遥か向こうにも浮かんでいる。氷山だ。船が進むにつれ、それらは後方へ流れ去っていく。新たな塊が視界に入ってきた。船から距離があるので、正確なことはわからないが、かなり大きい。
次から次へと現れる氷山は、夜が明けるにつれ、朝日を受け、次第に白さを増し、新雪をかぶった雪山のように輝き始める。海は限りなく青くなっていく。波はない。南極の海に近づいたようだ。
「昭和基地へ行くの?」。南極へ行くことを伝えると、多くの人が、そう問いかけてきた。無理もない。大半の日本人にとって、南極イコール昭和基地であり、タロとジロの物語なのだから。
だが、実際のところ南極圏とは、地理的にいえば、南極点を中心に南緯66度33分までの海域や島々を指し、日本のおよそ36倍もの広大な面積を持つ南極大陸が、その中心に存在している。南極大陸からは、南米大陸に向かって南極半島が細長く突き出している。この半島の先端部分への上陸と周辺海域が、今回のクルーズの主な目的地であり、昭和基地とは直線距離にして4000キロ以上離れている。南極はとてつもなく広大なのだ。
地球温暖化の影響を最も受けている場所。南極は、そのようにいわれることが多い。南極の氷がすべて解けたら、海面が40~70メートル(環境省サイト)上昇し、世界のいくつかの都市は水没するとも。
南極の自然に触れ、その美しさを手放しで楽しむ時代では、もはやなくなってきている。もちろん、専門家ではないので、南極で気候変動の兆候を自ら摑み取ることなど、できるはずもない。でも、わずかでよいので、何か感じることができれば。そんなことを漠然と思い、日本を発った。
ウシュアイアを出た船は、南極半島周辺を10日間ほどかけて航行し、乗客はいくつかの地点で、実際に南極大陸と周辺の島々に上陸することができる。一般観光客がクルーズ船で大陸に近づき、上陸までできるのは、南極の夏に当たる11月から翌年の3月末まで。夏といっても平均気温はマイナスで、沿岸部でマイナス10℃、内陸部ではマイナス30℃以下ともなる極寒の地であることには変わりがない。今回のクルーズが行われたのは、3月中旬から下旬にかけて。南極の夏の終わりの時季だ。
船の名前は20世紀初頭に南極を探検したフランス人冒険家の名にちなんだ「ル コマンダン シャルコー」。フランス唯一のクルーズ会社、ポナンが所有する、最上クラスのラグジュアリークルーズ船である。
船内で表示される外気温は、すでにマイナス5℃。南極大陸に上陸する日を迎えた。日本を発ってから100時間以上の時間が過ぎていた。
2.人間を恐れず気ままに歩くジェンツーペンギン
エンジン付きのゴムボートに10人ずつ乗り込み岸に向かう。上陸地点は、南極に生息する4種類のペンギンのひとつ、ジェンツーペンギンの営巣地だ。接岸し膝まで海に浸かりながら、注意深くボートから降り立つ。夏季のため、波打ち際は氷が解け、黒い石の砂利浜となっている。
ペンギンがいる! しかも数え切れないほど。歩くかと思えば止まり、海へ向かうかと思えば、急に方向を変えて陸地の奥へ進む。ゆっくり歩くときは羽を畳んでいるが、少しスピードを出す場合は羽を後方に広げてバランスを取っている。それは、小さな男の子が飛行機の真似をして、両手を広げて走る姿そのもの。ただ、短い足でのよちよち歩きには変わりなく、しかも足元がおぼつかなく転んでしまいそうで、実際に転んでいるペンギンもいる。単独行動しているものもいれば、3匹くらいで、同じ方向に進んでいる場合もある。腕白小僧たちが、「おい、あっちへ行こうぜ」と、はしゃぎながら駆け出しているみたいだ。
5メートル以内の接近は、南極条約で禁じられているが、人を怖がらず、ジャリジャリと音を立てて氷を踏みながら、目の前を通り過ぎていく。通り過ぎるペンギンは、人間の存在が眼中にないようだ。まったく無視している。闖入者(ちんにゅうしゃ)である人間を、ペンギンたちは恐れもしなければ、相手にもしない。人間を見ると逃げる野生動物を見慣れた我々にとって、それはとても新鮮な体験だ。そして思う。それほど遠くない昔、人間は地球の上では闖入者、遅れてきた生物にすぎず、圧倒的多数のほかの動物たちを恐れながら生息していたはず。その人間が、いつの間にか我が物顔で、地球を支配したつもりになっている。
2時間弱の大陸滞在の後、沖合に停泊している船へ戻る。ゴムボートが岸を離れると、小さなペンギンたちの姿は海岸の風景に溶け込み、すぐに見えなくなってしまった。
3.つぶらな瞳で見つめてくるオットセイの子ども
遠征を意味する「エクスペディション」と名づけられた、こうした船外活動は、午前と午後の2回行われる。南極オットセイの生息地に上陸した日もあった。
3月は夏に生まれたオットセイが活発に動き始める時季だ。ペンギンより好奇心があるのか、こちらに近づき、つぶらな瞳でじっと見つめ、時折小首をかしげるような仕草までする。哺乳類の赤ちゃんがもつ「可愛さ」という要素をすべて集めた、といっても過言でないオーラを発しながら、前脚を器用に使い、ハイハイする赤ちゃんのように動き回っている。その姿は、懸命に生きる無垢なる命そのものだ。
しかし、無力なオットセイは、かつて毛皮を得るために、年間何十万頭という規模で殺害された。そもそも、オットセイの毛皮を求めた漁師たちが、危険を顧みずに新たな海域へ乗り出していったことが、南極大陸や周辺の島々の発見につながっていったという史実を知ると、複雑な気分になる。遅れてきた闖入者は、勇敢ではあったけれど、欲深く凶暴な闖入者でもあった。
4.環境負荷を最大限減少させた最新鋭のクルーズ船
厚さ6メートルもの海氷を割って進む、客船としては世界初の最強機能をもつ砕氷船、それが「ル コマンダン シャルコー」だ。また、客船としてはやはり世界初の、LNG(液化天然ガス)もしくはディーゼルガスと、電気との併用によるCO2排出量削減など、環境負荷を軽減するためのテクノロジーを結集した、最新鋭のクルーズ船でもある。その一方で船内はすべてがラグジュアリー。環境への配慮とラグジュアリー、この二つが見事に両立している。
レストランは、気軽なビュッフェと、前菜、メイン、デザートを選んでオーダーするアラカルトスタイルの二つが設けられている。後者の料理はアラン・デュカス監修。牛肉のタルタル風、仔羊背肉のロティにトリュフやキャビア……。海の上と思えない料理と美しい盛り付けのフレンチが連日登場する。ビュッフェのメニューも日替わりで、デザートは街の一流パティスリーと同様のおいしさ。朝は焼きたてのクロワッサンに新鮮な野菜とフルーツ、ハムとチーズもふんだんに並ぶ。
船内で過ごしたのは28平米の「デラックススイート」。下から二番目のカテゴリーだが、ラグジュアリーホテルと変わりのない設備とこまやかなホスピタリティが、2週間を超す長い航海をストレスのないものにしてくれる。航海中に生じる汚水は、船内で100%クリーン化処理した後に排水されるので、環境にも優しい。屋内と屋外の二つのプール、スパ、サウナ、ジム、美容室、シアターなど施設も充実している。
いまから約110年前、生死を懸けて多くの冒険家が南極探検に挑んだ。そんな極地に足を踏み入れ、過酷な自然環境を束の間体験したあとは船に戻って熱いシャワー、そして冷えたシャンパンと極上のフレンチ。眩暈がするようなこんなギャップを味わうことができるのが「ル コマンダン シャルコー」である。
5.戻る場所のある動物たち。では人間の戻る場所は……
次々と現れる大小さまざまな形の氷山、一面の海氷に覆い尽くされた海、厚く積み重なった氷河とその奥に連なる純白の山並み、海まで迫る切り立った崖のような氷床……。千変万化する景色も南極クルーズの魅力のひとつだ。
氷河から突き出ている荒々しい岩盤を見ると、南極が大陸であることに、あらためて気づかされる。厚いところでは4000メートルもある氷の下に大地を潜ませながら、人間が近づくことを拒否する峻烈(しゅんれつ)な景色。そんな景色に何日も取り囲まれていると、人間は紛れもなくこの大陸への闖入者、いや、地球への闖入者でしかなく、その闖入者が地球を壊そうとしている……。ペンギンの営巣地でよぎった、あの思いに再びとらわれる。
日本から到達するまでの日数のことなどを考えると、南極は気軽に行くことができない場所であることは事実だ。しかし、ひとたび南極大陸に足を踏み入れ、動物たちに出合い、絶景を目の当たりにすると、人間とは、地球とは、環境とはと、普段あまり考えることのない、でもとても大切なことが自然と脳裏に浮かんでくる。南極クルーズは、そうした、またとない貴重な経験を与えてくれる。
流氷の上でのんびりくつろぐペンギンやアザラシの姿を、船上からときどき見かけた。氷上のピクニックのような、ほほえましい光景だ。でも、氷が海流によって流され、南極域を出るようなことがあれば、その前に動物たちは、敏感にそれを察知し、氷を離れて本来の棲み処へ戻っていくだろう。では人間は? 現実をきちんと察知しているのだろうか? 戻らざるを得ない場合、戻ることはできるのだろうか? 戻る場所は? 次第に暮れゆく、流氷に覆われた海をバルコニーから眺めながら、そんなことをふと思った。