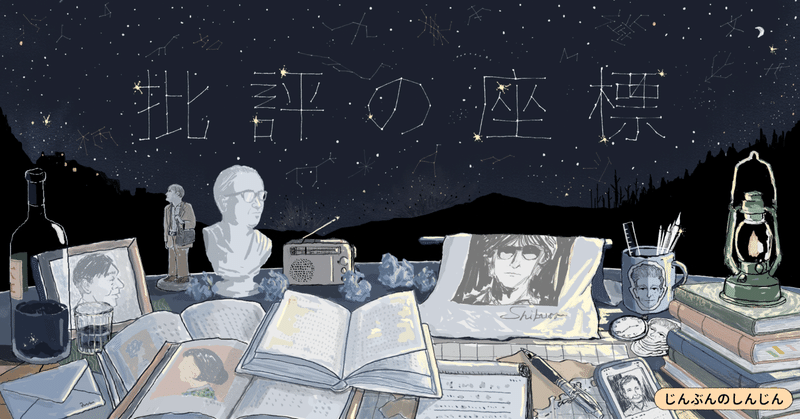
【批評の座標 第5回】「外」へと向かい自壊する不可能な運動──絓秀実『小説的強度』を読む(韻踏み夫)
近年のBLM(ブラック・ライヴズ・マター)からも垣間見えるように、ヒップホップと人種差別への抗議が連動する現代において、その批評や研究から出発し、『日本語ラップ名盤100』(イースト・プレス)を上梓した韻踏み夫。第5回では、現代史の転回点である一九六八年論の代表的な批評家・絓秀実を取り上げ、その主著『小説的強度』から、いま必要な理論的展開を描きだします。
――批評の地勢図を引き直す
「外」へと向かい自壊する不可能な運動
――絓秀実『小説的強度』を読む
韻踏み夫
「しばしば私にはヘーゲルが自明であるかのように思える。だが、この自明は担うには重い」(『有罪者』)。なぜ今日──今日においてもなお──バタイユの最良の読者たちであってさえ、ヘーゲルの自明性をいともたやすく担えるほど軽いものであるかのように考える人々の列に加えられてしまうのだろうか。(……)過小評価され軽々しく扱われたヘーゲル主義はかくして、その歴史的支配をひたすら拡大していくであろう。(……)ヘーゲルの自明性は、それがついにその全重量をもってのしかかるようなとき、かつてないほど軽く思えるのである。
1.
二〇一〇年代後半以降、絓秀実(1949-)という批評家への再評価が進んでいるかに見える。その要因は主に二つ挙げられるだろう。第一に、日本を代表する「六八年」の革命的批評家として。その評価は、絓の代表作と見なされているはずの『革命的な、あまりに革命的な』(2003)――二〇一八年に文庫化された――を筆頭に、『1968年』(2006)、共著を含めれば『LEFT ALONE 〜 持続するニューレフトの「68年革命」』(2005)、『対論 1968』(2022)などによって形作られている。次いで、絓はとりわけ二〇一〇年代以降顕著になったポリティカル・コレクトネス(PC)問題においても強く参照される批評家でもある。それは、『「超」言葉狩り宣言』(1994)や『「超」言葉狩り論争』(1995)の時期におけるジャーナリスティックな著作群によってである[2]が、同時に「華青闘告発」を大きく取り上げ、六八年の現代的帰結がPCであるとする六八年論とも密接に連関してもいる。つまり、絓は現在では、六八年と差別論の批評家として受け取られていると見てよいだろう。
しかしながら、初期――と便宜的に言っておく――の絓秀実とは他の何よりもまず、「昭和十年前後」(≒一九三〇年代)の批評家であった。デビュー作『花田清輝――砂のペルソナ』(1982)から始まり、『複製の廃墟』(1986)、『探偵のクリティック――昭和文学の臨界 絓秀実評論集 〈昭和〉のクリティック』(1988)を経て『小説的強度』(1990)に至る過程において、絓はこの、「昭和十年前後」という一時期に並々ならぬ関心を寄せ続けたのだった[3]――この点事情はきわめて複雑であるかに思われるが、ひとつだけ言っておくならば、共産党壊滅後の「昭和十年前後」の「文芸復興期」は、絓が文章を書き始めたポスト六八年の「大衆消費社会」の時代と、革命運動の退潮期という点で共通の時代性を有しているということは最低限指摘できる。
『小説的強度』は絓の最高傑作としてきわめて高い評価を受け続けてきた主著と見做しうるものであり、そこでは批評史上においても稀有な理論的達成が見られるということも疑いない。「初期」の絓は「昭和十年前後」を思考するなかで、大きく言って、「表象=代行機能の失調」(『複製の廃墟』)と「自己意識」(『探偵のクリティック』)という二つの問題に行きついていた――政治性の観点からのみ補足的に言えば、「表象=代行機能の失調」とは前衛(党)の不可能性の問題でもあり、「自己意識」とは転向の問題でもある。つまりこれらは、文学的な問題のみには収まらないものであり、ここに「後期」の絓の革命をめぐる思考との連続性を認めることは可能である。『小説的強度』はいわば、そこで得られた理論的精華を凝縮し、かつそれを縦横無尽に駆使してきわめて広大な知の領域――文学理論、哲学、経済学、政治思想、民俗学、人類学……――を横断する一冊であり、そのあまりにダイナミックで大胆な横断的記述こそ、本書の「批評的な、あまりに批評的な」魅力となっていることはたしかだ。他方、「あとがき」では、その理論的相貌に反して意外にもこれが「「時評」集として読まれれば、これに過ぎる喜びはない」[4]とも述べられている。それは、本書が書かれた同時代の状況、すなわちポストモダンの「大衆消費社会」への批判的分析という、具体性=実践性の色を強く持った書であることをも示している――実際、批評とは、理論と具体=実践のあいだで引き裂かれつつもがくことでなくてなんであろうか?このことを銘記したうえで、しかしここでは、あえてその具体性を捨象し、その理論的な側面にのみ焦点を当て、複雑かつ大胆に適用、変奏、連結される概念群の布置と運動の、ごく骨子のみを素描してみることにする。それは、その理論が、今度はわれわれの、そして未来の時代状況のただなかにおける具体性=実践性の闘争に再び移植され、用いられるべきだと考えるからである。
2.
『小説的強度』を特徴づけているのは、何よりもヘーゲルの「主と奴の弁証法」への異様なほどの執着である。一冊はほとんど、このヘーゲル弁証法の枠組みにもとづいて書かれていると言ってよい。すでに述べたように、それは「昭和十年前後」の問題から導出されたものだ。『探偵のクリティック』ですでに「世界史的に見て、一九二〇、三〇年代とは、それがヘーゲル的自己意識という問題を顕在化させた時代なのである」[5]と述べられており、むろんヘーゲルの「自己意識」論とは、「主と奴の弁証法」を指す。「『ヘーゲル読解入門』のアレクサンドル・コジェーヴに倣って言えば、「主」と「僕」の弁証法として展開されるヘーゲルの自己意識論は、その哲学体系の要として、市民社会論、美学、歴史学の全領域を――すなわち全人間的世界を――覆っていると言える」(強調傍点は引用者による、以下同様)[6]。『小説的強度』が様々な知の領域を横断するような形で書かれているのは、ヘーゲル弁証法自体がそのような「全人間的世界」という広大な射程を持つからである。
しかし、『小説的強度』において「主と奴の弁証法」は「自己意識」論というよりはむしろ「コミュニケーション」論であると、定義し直されている。「ヘーゲル「自己意識」論の卓越性とは、この「無媒介態」として設定された自己が、それ自身の論理的展開によって、自己表現と、他者とのコミュニケーションを成立させるにいたる過程を記述し、解明したところにある。(……)『精神の現象学』は、自己意識の成立において、表現とコミュニケーションが成立していく様を論じていると見做すことができよう」[7]。先に述べておけば、絓の目論見とは、このヘーゲル的「コミュニケーション」を乗り越えることである。しかしながら、そのために絓は、この「主と奴の弁証法」の運動に徹底的にまみれてみせるので、あたかも絓がヘーゲル主義者であるかのように見えてしまうほどだ。だがそれは、乗り越えるべき「ヘーゲル的枠組みの巨大さ」[8]がそれほどのものだからなのだと理解しておくべきであろうし、仮にヘーゲル主義者であるとしても絓は、デリダがバタイユに対して述べたような、「留保なきヘーゲル主義」者に近いような立場にこそ身を置いている。
いかにして「主と奴の弁証法」という「コミュニケーション」は始まるのか。はじめ自己は「自己自同的」であり、そこで相手を「否定的なもの」と見るので、「互いに他者を否定しようとして、「承認をめぐる生死を賭する戦い」に入らざるをえない」[9]。ここが、無媒介だった自己が他者と媒介し、「コミュニーション」が駆動し始める地点である。そこで何が起きるのかと言えば、「周知のように、(……)死を賭しえた勝者が主と呼ばれ、賭しえなかった者が奴(僕)と名づけられる」[10]。「主」と「奴」の分割であり、同時にそこに決定的な形で絡むのが「死」である。「そしてまた、主と奴のコミュニケーションを保証するコードも、死にほかならない」[11]。ここに、「コミュニケーション」の端緒が開かれた。
むろん、「主」と「奴」とは全般的な二項対立関係をあらわす用語であり、「主」は優位にあり、「奴」は劣位にある。具体例をここで一度列挙してみよう。主体/客体、西洋/東洋、オリジナル/コピー、政治/文学、資本家/労働者、「買う立場」/「売る立場」、男/女、理性/下層、……。これらの間の「コミュニケーション」を探査することが問題なのだが、周知のとおり「主と奴の弁証法」の要点とは、その「主」/「奴」の序列が逆転する運動が説明されていることにこそある。そこで絓は「欲望」ということを思考する。「欲望は、まず主において満たされる」[12]ことについては言うまでもないが、「主」の「欲望」を満たすために実際に「労働」するのは「奴」にほかならない。そして「主」の意図=「欲望」を「奴」が「代行」する=「労働」するということは、つまり「奴」が「欲望」から「疎外」されているということでもある(「労働疎外」)。しかし、その「労働」が蓄積されていくなかで、(「主」性としての)「欲望」は「奴」の側へと移り行くことになる。「奴の欲望は、死を延期する「時間」=労働として現実化していくのである。ここにおいて、奴は主への「畏怖」を失いつつある。主と奴の序列が逆転する契機がめばえているのだ」[13]。このようにして絓は、ヘーゲルの脱構築のために、ヘーゲル弁証法の論理展開にその果てまで付き合うことになる。本書で実際に用いられている言葉を借りれば、つまり「踏破しつつ批判する」[14]というのが、絓のヘーゲルへの戦略的態度なのである。
3.
この「労働」がきわめて重要な概念であることは言うまでもない。そもそも「ヘーゲルが人間の本質を技術=労働として捉えていた(……)」[15]からである。ならば「労働」とはなにか。端的にそれは、「奴」が自らの劣位性を「回復」するための運動に与えられた名前だと解しておいてよい。そしてその「労働」を駆動するエンジンとして、ニーチェ的な「恥」の問題が絡むことにもなる。「奴」は「主」に対して劣位に置かれており、そのことは、「遅れ」、「後れ」などとも言い換えられる[16]。ならば「奴」は自らの「遅れ」=劣位性を「恥じ」て、それを「回復」させようとするだろう。しかし、この一見ごく自然な運動の力学自体に批判的な目を向けるのがニーチェ的視角であり、それはヘーゲル批判の前提ともなるだろう。「「奴」は「主」を模倣するが、しかしそのことによって「奴」であるのではない。そうではなく、模倣を恥じることによって「奴」となるのである。あるいはまた、「奴」は「主」を模倣しながらも、それを自ら恥じることによって、逆にその恥を隠蔽しようとする。(……)「奴」につきまとう恥の意識をニーチェに倣って「疚しい良心」とも呼びうる(……)」[17]。そしてこの「恥の意識」=「疚しい良心」がエンジンとなり、「労働」(劣位性の「回復」運動)が駆動するのである。なお述べておけば、それに対する絓の基本的な戦略とは、単純化して言うなら、そもそも劣位性を恥じなければよい、というようなものである。
「労働」が「遅れ」を「回復」する運動一般のことを含意するというのは、単にそれが経済学的な範疇のみには収まらないということでもあり[18]、たとえば、その「労働=技術」というヘーゲル的人間観が文学論に適用されるならば、「その時、労働=技術という小説=文学の本質は、表現という水準において抽出されなければならないことになるだろう」[19]と、つまり「労働=表現」の等式が成立することになる(「表現」=「表象=代行」論的文学観への批判)。たとえば具体的には、「政治」を、あるいは「実生活」を、「文学」が「労働=表現」するというような――および、その「主」/「奴」を逆転させたヴァージョンとして、政治や実生活に対して「文学の自律性」を主張するような――支配的なパースペクティヴへの批判を絓は基本的な問題意識として有している[20]。この「労働」批判について最も重要なのは、その論理的な前提であり、それは次のようなものだ。「すなわち、労働=表現は疎外としてしか体験されえず、そしてまた、その疎外は労働=表現によってしか回復(止揚)しえないというヘーゲル=初期マルクス的な――二重の疎外の二重の否定による止揚の――磁場(……)」[21]である。
だから、絓の問題意識は一貫して、このような疎外―回復という図式の外側へと脱出することにほかならないが、しかしそこで特徴的なのは、その脱出の困難へのきわめて強い自覚と警戒であり、その「磁場」の抜け出しがたさをあまりに執拗に描くので、むしろ読む者にその外部は不可能なのだと主張していると錯覚させてしまうほどなのだ。
しかしそのことすら、すでに本書の概念装置の中に組み込まれていると言える。ヘーゲル的体系からの脱出の困難を示しているのが、「悪循環」概念であるだろう。「奴」の「労働」の蓄積によって「主」が乗り越えられ、序列の逆転に成功すれば事は済むのかといえば、そんなことはまったくない。もし、「奴」の「労働」による「主」の殺戮、すなわち「王殺し」(典型例はむろんフランス革命)が成功したらどうなるのか。問題は、「王殺し」後においても、「主と奴の弁証法」という「コミュニケーション・システム」自体はいささかも揺るがないことである。「主」が死んでも、「奴」の間で再び「承認をめぐる生死を賭する戦い」が行われ始めるだけだからである。
「王殺し」の後には何が起きるか。「王殺し」の後には「奴」のあいだに「罪の意識」――それは「王殺し」以前に「奴」が「主」に対して抱いていた「恥の意識」が反転したものだろう――が芽生えることになる。「しかし、主の意図なくしては、奴は表現すべきものを持たない。それゆえに、主がいかなる形であれ死んだ後には、奴は罪の意識を必要とするのである。だとすれば、労働=表現自体が、「悪循環」にほかならない」[22]。その「罪の意識」から「奴」は「オリジナル」を再び措定するという「悪循環」に入ることになるのであり、ゆえに「労働」概念ではヘーゲル的「コミュニケーション」の外への脱出は不可能なのである。この「悪循環」の感覚に徹底的にまみれながら、粘り強くその外部を切り開こうとすること。ではいかにして外部は垣間見られることになるのか。
4.
そこでヘーゲル体系の脱構築のための有効な戦略として肯定的に取り上げられるのが、「フェティシズム」である。足掛かりとなるのは「否定」概念である。まず、「労働=表現」とは、「死の恐怖」に屈した「奴」が「主」を「否定」する運動だとも換言できる。「このことは、「死の恐怖」こそが奴的否定の運動の動力であることを意味していたが、その動力は、労働として、あるいは表現として発現したものである」[23]。
そのうえで絓は、このヘーゲル的「否定」を、フロイト的「否定」と重ね合わせてみるという操作を施す。「このように考えると、ヘーゲル的否定の概念をフロイト的否定の概念に置き換えてみることが可能になる。奴が否定しようとしているのは、「死の恐怖」としての「去勢」だと言えはしまいか。われわれは――すなわち、奴は――去勢を否定しようとして、労働=表現におもむくのだが、だとすれば、去勢の否定として表現されたイメージ=偶像が、男根であることは言うまでもない」[24]。「死の恐怖」と「去勢」の論理的共通点とはなにか。それは私たち「奴」が、つねにすでに「主」的なもの、起源やオリジナル(「死」および「男根」)を喪失しており、そこから「疎外」された存在だと規定することにある。だからここでも、疎外―回復(=「否定」)という図式が共通しているわけだ。
このときフロイトは「否定」と「否認」という二つの概念を区別しているのだから、議論は今度は、おそらく『マゾッホとサド』のドゥルーズを暗黙の参照項としつつ、「否認」の方へと向かうことになる。「否認もまた、去勢に関わるフロイト的概念である。否定が男性的な構えであるとすれば、否認はおもに女性とフェティシスト、精神病者の構えである」[25]。絓は別の箇所で、「改めて主―奴なるヘーゲル的コミュニケーション・システムをながめてみると、主も奴もともに「男」であることが暗黙の前提とされていると知られる」[26]と述べていたのだから、つまり「主と奴の弁証法」自体がすでに「男性的な構え」である。その男根中心主義を批判するために、「否認」という非「男性的な構え」が思考されているのでもある。「男性とは、否定によってイメージとして再建された男根に、直接的にリビドー備給する存在だと言える」のに対して、「ところが、女性あるいはフェティシストは、去勢という現実を拒否すると同時に、それを承認するのである。この分裂した二つの態度の共存が、去勢の否認にほかならない」[27]。
だから、なぜ「否認」を実行する「フェティシスト」に重要性が置かれるのかと言えば、それは以下のようになる。「否定」とは、上で確認した、「奴」が劣位性を「回復」し、なにかを「再建」しようとする運動と同義である一方、「否認」はその支配的な運動から逸脱し逃走してゆく運動にほかならないからなのだ。「この承認と拒否の二重性――差異――が否認の強度を産出する。(……)フェティシストはロマン主義者の隣にいながらも、それを根底的に批判するのだ。ロマン主義者は、最終的には、イロニーという技術を用いて、ポイエシスとしての労働=表現の再建を目指しているが、フェティシズムは、ただ技術として、つまり方法として存在することができるだけだからである」[28]。「否認」とは何かを「再建」する定立的な運動ではなく、閃光のように「強度」を垣間見せるだけであり、それゆえに「技術」=「方法」[29]としてのみ存在しうるだけである。しかしながら、そこにおいてこそヘーゲル体系の「外」への細い道が現れる。ここでは、「フェティシズム」とは、主と奴の弁証法の内部から外部へと割って出る、微かにのみとらえられる運動にほかならないのだ。
5.
ここで「技術」と「強度」という重要な概念が登場している。まず、絓は「労働=技術」という等号を組むヘーゲル的発想に反して、「技術」を「労働」から分離したブランショについて検討していた。「ブランショの言うオデュッセウスの技術から、注意深く労働という概念が消去されて」いるので、「ブランショにおいて小説を特徴づける技術は、労働との間の等号を抹消されていると言ってよいだろう」[30]。小説の「起源」とは、という問いにおいて、ヘーゲル的パースペクティヴからすればそれはおおむね、「労働=技術」の蓄積において「起源」あるいは本来性を「回復」することが問題となる一方、ブランショは「技術(≠労働)」としての小説を、「起源からの隔たり」[31]と見做し、発想を逆転させたのであった。つまり、この文学論においても、やはりヘーゲル体系の「外」が目指されているわけだ。「われわれがブランショに倣い、ヘーゲルに逆らって、それは技術ではあるが労働ではないと言ってきたのは、その「外」を名指すための暫定的な措置であった」[32]。
ここに見られる「技術」の自立という問題は、章を跨いでロシア・フォルマリズムについての分析へと持ち越されることになるだろう。文学の形式性をめぐる理論を洗練させ、フランス文学理論にも絶大な影響を与えたロシア・フォルマリズムとは、「言葉の道具化を逆手に取った技術の顕揚であることは疑いない」のであり、道具化や疎外を批判する「初期マルクスやハイデッガーの構えとは反対の方向を指している」[33]。もう少し言うと、ロシア・フォルマリズムは「技術の自立化の側に立っている」のであり、「詩的イメージはすでに問題ではなく、ただ、いかにして書くかという技術のための技術こそが芸術上の価値を決定するということになる」のであり、「この時、言語による表象としてのリアリズムの前提は崩壊して、芸術なるものは内容(イメージ)を持たぬ空虚な形式(技術)を逆説的に内容としようとする、不可能な技術となる」[34]。
独特なのは、絓がこのフォルマリズム的「技術」をニーチェ的「強度」と接続しようとすることである。リアリズムと「芸術のための芸術」の双方を批判するニーチェにとって、芸術とは「「強度」――として――のコミュニケーションにほかならないと言われる」[35]が、シクロフスキーが問題としたのも「実は、イメージを欠いた強度そのもののコミュニケーションなのである」[36]とされる[37]。この箇所が理論的重要性を担っているのは、本書の最大の課題であったヘーゲル的「コミュニケーション・システム」とは別の、その「外」(ブランショ=フーコー的な)の「コミュニケーション」の存在が、ようやく記述されているからである。
同時にここにおいて、本書で一貫して問題となっていた「コミュニケーション」概念の裏側も明らかになったと言える。絓自身は明示していないはずだが、本書の「コミュニケーション」とは、ブランショ=バタイユ的な概念だったのである。モーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』[38]の西谷修による「コミュニケーション」概念についての訳注を参照すれば、communicationには少なくとも「伝達」と「交感」という二つの訳し方が可能である。そしておそらく絓は「伝達」的「コミュニケーション」をヘーゲル的なそれと重ねており、「強度そのもののコミュニケーション」が「交感」的「コミュニケーション」に当たるだろう。西谷は実際、「交感」的な含意の方について、「この訳語(「交感」―引用者)は、知から〈非-知〉への移行のうちにある、絶対知という知的体験の極限が感性的強度として生きられる恍惚へ滑りゆく局面をよくとらえており」というように解説している。そこでは主客が消滅し「ここには伝えるべきものは何もなく、ただ「恍惚が」それ自体「交感するcommuniquer」のである」[39]とされており、まさしく「強度そのもののコミュニケーション」という絓の記述と響き合っている。言い換えれば、『小説的強度』の理論的な背骨とは、ヘーゲル的「コミュニケーション」に対して、ブランショ=バタイユ的な「コミュニケーション」の二義性を突破点としてその外部を切り開き、そこにおいて「強度そのもののコミュニケーション」を見出そうとするものだったのである。
最後に、この「初期」の絓の理論と、近年の「革命的」相貌を色濃くした絓とを結び付けておくべきだろう。『小説的強度』の理論を革命論に適用するならば、一般的な革命概念は根本的な変容を被らざるをえない。つまりここでは、「奴」による「主」との序列逆転は問題ではなく、革命とは、真に、「外」の「強度」を切り開くことを指すようになるからである。言うまでもなく、それこそ六八年世界革命が布告したことであり、フランス現代思想の前提ともなっていることである。しかし、そうした「強度」とは「批評」そのものを自壊させてしまうようなものにほかならない。「ここにおいて――すなわち、表現からの技術の自立化という事態において――少なくとも批評は、ある困難に逢着する。強度を、リビドー備給されたイメージ対象によって評定できないならば、作品の言葉はいったいどのようにして読みうるというのであろうか」[40]。いまや、「批評」とは、「強度」や「革命」といった「不可能」なものへと向かい続け、その果てに自壊してゆく運動のことを指すようになった。ここにおいて批評と革命的政治運動は運命をともにすることになるのだし、あらゆる「批評」が「革命的」であらねばならないのもそのためだ。この真に「革命的」で、「批評的=臨界的」な瞬間へと向かう運動を反復=継続すること。
実際、この後、批評および現代思想では、この言語化不可能の厄介な「外」をいかに処理するかが問題となったと言える。ここでの文脈に沿って言えば、語りえない「外」の「強度」は、再び「主」として措定されヘーゲル的体系に取り込まれるのではないか、と要約しうるものだ。東浩紀の「否定神学批判」に代表されるだろう。その正当な批判はしかし同時に、「外」=「革命」を縮減し、馴致しようとする身振りでもあったのではないか。こうも問おう。その政治的帰結として、批評は社民的改良主義へと路線変更しはしなかったか。それは外部なき「資本主義リアリズム」(マーク・フィッシャー)をもたらしたグローバル資本主義以後の経済的土台の上にこそ成立する思考なのではないか。しかしながら、いやそうであるからこそ、いかに困難な営為ではあれ、私たちはいまこそ、再びみたび、「外」=「革命」の権利を要求し証明し続ける必要があるし、そうした――理論的かつ具体=実践的な――批評が書かれ/読まれ続けねばならないはずなのだ。
[1] 『エクリチュールと差異』、合田正人・谷口博史訳、法政大学出版局、二〇一三年
[2] それは近年出版されたPC論である、千葉雅也、二村ヒトシ、柴田英里『欲望会議 「超」ポリコレ宣言』(二〇一八年)、綿野恵太『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(二〇一九年)などに引き継がれていると言える。
[3] 「昭和十年前後」という用語はもともと平野謙によるもの。それへのこだわりについて、絓自身こう述べている。「ベンヤミンの「第二帝政期」狂いには及びもつくまいが、実際に生きたわけでもない一九三〇年代を、あたかも自分の同時代であるかのように思い込んでしまう感性は、『花田清輝――砂のペルソナ』を書きつつあった時以来、日に日に強まっているようだ。一九三〇年代、あるいは平野謙の言う「昭和十年前後」における、言葉の表象(再現)機能の失調といった出来事が、現代の、大衆消費社会とも呼ばれる「複製技術時代」を生きる者にとって、他人事とは思えないのである。ベンヤミンが――あるいはバタイユやブランショが──生きた一九三〇年代が、私にとっての「第二帝政期」のように感じられる。」(『複製の廃墟』、福武書店、一九八六年、二八〇頁)
[4] 『小説的強度』、福武書店、一九九〇年
[5] 『探偵のクリティック』、思潮社、一九八八年、二二頁
[6] 同上、一七頁 なおこの段階では「「主」と「僕」の弁証法」と表記されるが、『小説的強度』においては「「主」と「奴」の弁証法」と改められ、そのうえで「奴」と「僕」のあいだには概念的区別が設けられている。「労働によって主と奴の序列を逆転した時、奴は僕(ぼく、しもべ)という主体になるだろう」(一〇二頁)。
[7] 『小説的強度』、八八頁
[8] 同前、九五頁
[9] 同前、八九頁
[10] 同前、九〇頁
[11] 同前
[12] 同前、九八頁
[13] 同前、一〇一頁
[14] 同前、九〇頁
[15] 同前、六九頁
[16] 同前、「小説の方へ――「昭和十年前後」のプロブレマティックをめぐる二つのイントロダクション」を参照。なお、「遅れ」概念はすでに、『探偵のクリティック』所収「前衛と遅れ」において論じられており、ここでも、「遅れ」を回復しようとしないこと、という基本的戦略は通底している。
[17] 同前、二〇―二一頁
[18] 逆に、経済学的な「労働」概念の検討は第四章「疚しさと価値形成」においてなされる。
[19] 『小説的強度』、七六頁
[20] たとえば、「プティ・ブルジョア・インテリゲンツィアの背理」(『複製の廃墟』)では、政治/文学を分節するパースペクティヴを果てまで生き、それが脱構築される地点まで進んだ平野謙の姿が描かれ、肯定的に評価されている。
[21] 『小説的強度』、八〇―八一頁
[22] 同前、一一七頁
[23] 同前、二一一頁
[24] 同前
[25] 同前、二一二頁
[26] 同前、一一八頁
[27] 同前、二一二
[28] 同前、二一三
[29] この「方法」概念は、シクロフスキー「方法としての芸術」(後述)、および竹内好「方法としてのアジア」(「方法としてのフェティシズム」の章を参照)を意識したもの。
[30] 『小説的強度』、七〇頁
[31] 同前、六四頁
[32] 同前、七四頁
[33] 同前、一九六頁
[34] 同前、一九七頁
[35] 同前、一九九―二〇〇頁
[36] 同前、二〇〇頁
[37] 正確に言えば、ニーチェ的「強度」とシクロフスキーのそれとは、前者には「情動性」があり後者にそれがないという点で、いささか些細な相違がある、とはされている。
[38] 西谷修訳、朝日出版社、一九八四年
[39] 同前、一五二―一五三頁
[40] 『小説的強度』、二〇一頁
関連書籍
著者プロフィール
韻踏み夫(いんふみお)ライター/批評家。94年。福岡県。著書『日本語ラップ名盤100』(イースト・プレス、2022年)。連載「耳ヲ貸スベキ――日本語ラップ批評の論点――」(2021年~2022年、文学+WEB版)、「フーズ・ワールド・イズ・ディス――ヒップホップと現代世界――」(2023年~、文学+WEB版)。論考「ライマーズ・ディライト」(『ユリイカ』2016年6月号)、「渡部直己の「弟子」としての体験を書き記す」(『対抗言論 反ヘイトのための交差路 3号』、2023年)、「ひとつではないヒップホップの性」(『ユリイカ』2023年5月号)など。
次回は7月6日(水)更新予定です。森脇透青さんが東浩紀を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
