
グローティウス『戦争と平和の法』試論
はじめに
本稿では,フーゴー・グローティウス(Hugo Grotius, 1583–1645)の主著『戦争と平和の法』(De jure belli ac pacis)の読解を試みる.
グローティウスは,今日では「国際法の父」として知られている.しかしながら,山内進(1949–)によれば,近年ではこの点に異論が提出され,最新の研究においてはもはやグローティウスは「国際法の父」とはみなされていないという(山内2009および山内2018).その異論を提出した有名な法学者の一人にカール・シュミット(Carl Schmitt, 1888–1985)がいる.シュミットによれば,グローティウスが国際法上の戦争ではない「私戦」(これ自体が中世的概念である)を〈戦争〉の範疇に数え上げており,その限りでグローティウスを「〔近代的な〕国際法の父」と呼ぶことは相応しくないというのである(シュミット2007)*1.
もちろん「国際法の父」の肩書が遡ってグローティウス以外の人物に割り当てられたからといって,グローティウスの重要性が減じることになるわけではない.ルソーが『社会契約論』でグローティウスを度々批判しているのは,グローティウスの法理論が中世的であったからではなく,実際に近代市民社会においてそれだけ影響力と実効性を有していたからではないか*2.その限りで,グローティウスの著作が近代法理論形成の土台を用意したことは疑いようがない.したがって,筆者としては,柳原正治(1952–)の次の見解に与したい.
『戦争と平和の法』の最大の目的である,法による戦争の抑制は,グロティウスの存命中はもちろん,その死後も,現実の世界で達成されることはなかった.その意味ではこの著作は成功を収めたとは言えない.ところが,戦争論はいうまでもなく,所有権,婚姻,契約,刑罰などの私法上の多くのここの理論に対しても,本書が及ぼした影響は,甚大なものであった.グロティウスと同時代の,または,かれ以後の学者たちは,グロティウスの理論を全面的に肯定するかどうかは別にして,つねにそれを念頭に置きつつ自己の体系構築に努めた.「国際法の父」または「自然法的私法論の父」という名称は,それ自体には必ずしも学問上の正確さはないにしても,本書が獲得した理論上の圧倒的成功を表現しているものであるとは言えるのである.
その上で,やはり我々が行うべきことはグローティウスの著作を虚心坦懐に読み解くことではないだろうか.喜ばしいことに今年に入ってから,グローティウス『海洋自由論』の新訳が出版されている(グロティウス/セルデン2021).「国際法の父」という肩書を一度外しつつ,「国際法」の枠内にとらわれない視点でグローティウスを読み解くのも面白いかもしれない.
グローティウス『戦争と平和の法』
グローティウス『戦争と平和の法』は,初版(1625年)をはじめとして,その後グローティウスの生前に改訂が加えられた第2版(1631年),第3版(1632年),第4版(1642年),および死後出版となった第5版(1646年)がそれぞれ出版されている.
グローティウス法学の体系性
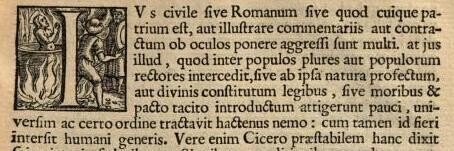
ローマの国法であれ,その他いずれかの国の法であれ,国家の法〔ius civile〕を註解によって説明しようとした者,あるいは要約して提示しようとした者は少なくない.これに対して,多くの諸国民の間もしくは諸国民の支配者たちの間に存在する法については,それが自然そのものに由来するものであれ,あるいは神の法によって定められたものであれ,あるいは慣習や黙示の含意によって導入されたものであれ,これに取り組んだ者はわずかである.まして,これを包括的に,また一定の順序に従って論じた者は.いままでのところ一人もいない.しかしながら,もしこれが実現されるならば,それは人類全体の利益となるであろう.
ここには大きく分けて二つの「法 ius」がある.一つが「国法 ius civile」*3であり,もう一つは「多くの国民の間もしくは国民の支配者たちの間に存在する法」である.今風の言い方をするならば,前者を国内法,後者を国際法と言い換えられるのではないか.さらにグローティウスは法の種類として(いわば法源の相異に従って),自然法*4,神の法*5,慣習法の三つに分けていることがここから伺える.
なるほどここでグローティウスが述べようとしているのは,この著作の意義である.国際法に関して「これに取り組んだ者はわずかである」というのだから,全く居なかったわけではないのであろう.しかしながら,「これを包括的に,また一定の順序に従って論じた者は.いままでのところ一人もいない」と述べている通り,グローティウスはまさに本書で先陣を切って国際法をいわば一つの体系として取り纏めることに主眼を置いていたと言えるであろう.実際,本書の持つ体系性は,プーフェンドルフ,スピノザ,ライプニッツ,ヴォルフなど,後世に多大な影響を与えたのである(山内2018: 419).
グローティウスの「社会的結合への欲求」とストア派の「オイケイオーシス」
グローティウスは,「戦争と平和の法」に関する古典古代の哲学者たちの見解を引き合いに出している.その中で批判されているのは,カルネアデース(Καρνεάδης, 214/3–129/8 BC)の次のような見解である.
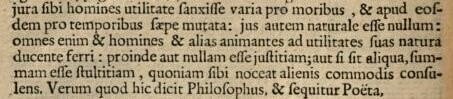
すなわち,人間は自分たちの利益のために自分たちに対して法を制定したが,その法は習俗によって異なり,同じ人々の間でも時に応じてたびたび変化する.また,自然法というものは存在しない.なぜなら,人間もその他の動物も,すべて,自然に導かれて自己の利益へと駆り立てられるからである.それゆえ,正義〔justitiam〕などというものは存在しないか,あるいは,もしなにかそのようなものが存在するとしたら,それは,愚昧のきわみである.なぜならば,他人の利便をはかることは,自分自身の利益を害することなのだから.
カルネアデースの見解によれば,絶対的な法は存在せず,人間を含む動物は本性的に自己利益を追求するが故に,自然法も正義も存在しない.これに対してグローティウスは次のように反論する.
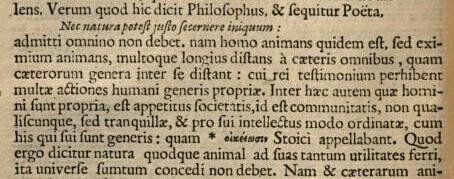
しかし,ここでこの哲学者〔カルネアデース〕がいっていること,またこれにしたがって,ある詩人が,
「自然は,正と不正とを判別することができない」
と述べていることは,決して容認されてはならない.なぜなら,人間はたしかに動物であるが,しかし格別な動物であって,他のすべての動物とは大いに異なっており,その違いは,他の動物たちの種が相互に異なっているのよりも,はるかに大きいからである.この点に関する証拠は,人類に特有の多くの行動がこれを示している.さらに,人間に特有のものであるこれらの行動の間には,社会[的結合]への欲求〔appetitus societatis〕,すなわち共同生活への欲求がある.ただし,それは,どのようなものでもよいというわけではなく,平穏な,そして人間知性のありように応じて秩序づけられた,同類である人々との共同生活である.ストア派の学者たちは,これをオイケイオーシス〔οἰκείωσιs〕と呼んだ.したがって,すべての動物は,自然によって,もっぱら自分の利益[を追求するよう]に駆り立てられるといわれていることは,人間を含めた一般的な意味で受けとめられる限り,承認されてはならないのである.
グローティウスによれば,「人間 homo」という動物は,他の動物と区別されるべき「格別な動物 eximium animans」である.その証拠として挙げられるのが,ストア派の「オイケイオーシス οἰκείωσιs」という概念である*6.
先に槍玉に挙げられたカルネアデースは自然法を否定したとされていた.これに対してストア派の思想史上の意義は,彼らが自然法論を初めて本格的に展開したことにあるとされている(青野1985: 163).
ここで人間を他の動物と分かつ特徴である「社会[的結合]への欲求〔appetitus societatis〕,すなわち共同生活への欲求」は,一見するとアリストテレス的な社会性のようにも思われるのだが,ストア派の人間観が,そのようなポリス中心の人間観とは大きく異なっている点を見逃してはならない(青野1985: 160).
(つづく)
注
*1: グローティウスに先立つ近代国際法の先蹤として評価されているのが,フランシスコ・デ・ビトリア(Francisco de Vitoria, 1483–1546)の死後出版の講義録(De Indis, De Jure Belli),バルタザール・アヤラ(Balthazar Ayala, 1548–1584)の『戦争の法と義務および軍隊の規律について』(De jure et officiis bellicis et disciplina militari, 1582),アルベリコ・ジェンティーリ(Alberico Gentili, 1552–1608)の『戦争法論』(De Jure Belli Libri Tres, 1598)である.
*2: ルソーによるグロティウス批判について詳しくは明石1998をみよ.
*3: 「国法」についてグローティウスは本書第一巻第一章ⅩⅣで次のように述べている.「国法とは,国家的権力〔potestas civilis〕に由来する法である.国家的権力とは,国家を支配ないし管理する法である.また,国家とは,自由な人間からなる完全な団体である.」(Grotius1646: 6,渕2011: 245).
*4: 「自然法」についてグローティウスは本書第一巻第一章Ⅹで次のように述べている.「自然法は正しい理性の命令である.それは,ある行為が[人間の]理性的な本性そのものに合致しているか,あるいは合致していないかということに基づいて,その行為が道徳的に恥ずべきものであるか,あるいは道徳的に必要なものであるかを示し,したがってまた,そのような行為が自然の創造主である神によって禁止されているのか,あるいは命じられているのか,ということを示している.」(Grotius1646: 4,渕2011: 235).
*5: 「神法」についてグローティウスは本書第一巻第一章ⅩⅤで次のように述べている.「神意法〔ius voluntarium divinum〕とはなにか.われわれは,それを,その言葉の響きそのものから十分に知ることができる.それは,もちろん,神の意思に起源をもつ法のことである.そして,この法は,神の意思を起源とするという違いによって,自然法(ちなみに,われわれは,先に,自然法は神法と同じだということができるといったのだが)と区別される.また,この[神意]法については,アナクサルコスがきわめて漠然と語った次の言葉,すなわち「神は,それが正しいがゆえに欲するのではなく,神が欲するがゆえに,それが正しいとされる.すなわち,それが法によって義務づけられるのである」という言葉があてはまる,ということができよう.」(Grotius1646: 7,渕2011: 246).
*6: 「οἰκείωσιs(オイケイオーシス)という言葉は,語源的には〈家〉を意味するギリシア語 οἶκος に由来しており,トゥキュディデス(4, 198)にみられるように,本来〈専有 appropriation〉という意味で使われていた.しかし,S・G・ペムブロゥクによれば,ストア派にあってはこの語は「専有するという能動的な意味で用いられることは決してなく」,この語が意味するのは,〈結び付き relationship〉であり,しかもそれは主観的要素すなわちそうした関係の意識ということにもっとも力点がおかれたいた.」(青野1985: 155〜156).
文献
明石欽司 1998「ルソーによるグロティウス批判—ルソーの近代国際法理論検討の契機として—」新潟国際情報大学 情報文化学部『新潟国際情報大学 情報文化学部 紀要』第1号.
渕倫彦 2010「訳註:グローティウス「戦争と平和の法・三巻」(Ⅰ)—「献辞」および「序論・プロレゴーメナ」—」帝京大学法学会『帝京法学』第26巻第2号.
渕倫彦 2011「訳註:グローティウス「戦争と平和の法・三巻」(Ⅱ・完)—「第1巻,第1章」および「人名表」—」帝京大学法学会『帝京法学』第27巻第1号.
柳原正治 1991「ヴォルフの国際法理論(二)—意思国際法概念を中心として—」九州大学法政学会『法政研究』第56巻第2号.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
