手慰みの練習曲を“小唄”に育てたベースとギターの“コロナの想ひ出”(加藤真一インタヴュー)

エチュード(Etude)とは、音楽の世界では“練習曲”を指しています。
一方、絵画や彫刻においては、完成作のための下絵や習作を指し、演劇においては、場面設定はあるもののセリフや動きは役者任せ、つまり即興劇のことだったりします。
いずれも“本番を念頭に置いた準備段階”というニュアンスを込めてつかわれることが多い言葉であり、それ自体を公に発表することは憚られるというか、“舞台裏”だから表に出さないほうがいいという風潮があるように感じていました。
ところが加藤真一の新作は、そんな芸術分野での忖度おかまいなしに、堂々とタイトルに冠し、しかも内容は余人がおよそ“練習曲”としてなぞらえることができないものを完成させてしまったのです。
「時間はたっぷりあったから、譜面を引っ張り出してきて練習していたんだけど、そればっかりじゃ飽きちゃったんだよね(笑)」(加藤真一)
いやいや、飽きちゃっても、それを作品にまで昇華させることができるなんて、並みの人にはできません。
ということで、“練習曲”をジャズってしまった『エチュード』が生まれる背景について、語ってもらうことにしました。

♪ 自粛期間の暇つぶしに手を出したのが練習曲
──2020年のはじめのころの活動って、どんな感じでしたか?
3月の半ばぐらいまでは、前年と変わりませんでしたね。2月にはドイツからピアニスト(註:クリストフ・サンガー)が来日して、ツアーをしていましたから。
ただ、そのころすでに、ヨーロッパではコロナが広がっているという話はしていましたけど、日本では大丈夫だった。
ところが、3月後半からのライヴが全部キャンセルになっちゃいました。
──東京オリンピック・パラリンピックの延期(註:3月24日に当時の安倍首相とIOCバッハ会長が電話会談で合意したことを発表、3月30日にIOC臨時理事会で正式決定)からガラッと空気感が変わりましたよね。
そうでしたね。
──自粛期間中はなにをされていたのですか?
まぁ、ポロポロと仕事はあったので。それと、配信をしたり。でも、あとはなにもナシ。
毎日、散歩するしかなかったですよ。たまに泳ぎに行っていたプールも閉められちゃったから、ストレッチとか散歩ぐらいしかできなかった。
おかげで近所の地理に詳しくなりました(笑)。
──ほかのミュージシャンからも、時間があるから練習して、だいぶ腕が上がったなんていう話を聞きました(笑)。
確かに、練習はしました。昔やったエチュード(練習本)を引っ張り出してきてね。コントラバスのエチュードだけじゃなくて、チェロのもやったりしました。
チェロのエチュードって、わりとメロディックなものが多いから、楽しいんですよ。でも、それも続けていると飽きてくるので……。
──ついつい、譜面から外れていった?
そうそう(笑)。で、なんとなくそのままスウィングしたりして、遊んでいるうちに、「あ、これ、おもしろい!」って思った。
それで馬場(孝喜)君に、「こんなアイデアを思い付いたんだけどやってみる?」って。彼を家に呼んでやるようになったんです。
ライヴ配信もやってみたんですけれど、観た人が「おもしろかった」って言ってくれたので、だったらカタチにしてみようかな、って。
──馬場孝喜さんとは前からのお知り合いですか?
B-HOT CREATIONS(註:加藤真一のリーダー・バンド。2004年『エンドレス・ジャーニー』、2005年『セット・ミー・フリー』、2012年『B-HOT CREATIONS』をリリース)のNobie(ヴォーカル)の紹介。
彼女が馬場君とブラジル音楽をやっていたので、それで仕事のときに来てもらったらおもしろかったので、それ以来。
ずいぶん昔のことですけどね。
──「ちょっと来てよ」って言うと、来てくれる間柄だったんですね。
うん。彼は断わらないからね。断わられたらやめたけど(笑)。
彼はどんな仕事を頼んでも、嫌な顔をせずにやってくれるから、僕としては好印象なんです。
なんといっても、巧いからね。どんなタイプの音楽でも大丈夫だし。
──そうやって始まったものが、こうしてアルバムになるわけですけれど、タイトルを目にすると、楽器をやっている人なら「なにをしようとしているのかな?」だったんじゃないかと思ったんです。
え? そうですか……。そうなのか……。
──練習曲というとクラシックのイメージだし、それでジャズをやるといえば、例えばオイゲン・キケロ(註:ルーマニア生まれのピアニスト。1965年に制作した『ロココ・ジャズ』を皮切りに、クラシックの曲をジャズに仕立て直すスタイルの第一人者として知られた)みたいな……。
あ〜、はいはい。
──そっち系なのかなって。でも、聴いてみるとぜんぜん違う。内容としては、まったくのジャズのデュオ・アルバムですよね。
そうそう。オイゲン・キケロみたいなやり方だと、クラシックの元の曲がシッカリあって、まとめ方もちゃんとしているじゃないですか。
コッチはもっと気楽というか、ね。
──モチーフになっているセバスティアン・リー(1805年生まれ)とフリードリヒ・ドッツァウアー(1783年生まれ)は、いずれもその名を冠した教則本がチェロ奏者には知られた存在だそうですね。加藤さんも使っていたんですか?
ちょっとだけ、やってましたね。ベースの練習をしていたときに、こういう教則本もあるよって教えてもらったんです。
ベース(=コントラバス)はチェロの教則本を1オクターヴ下で弾くことができるので、譜面としてはそのまま流用できるんですよ。
ただ、チェロはベースより低い音が出るので、ベースでは書かれたとおりには弾けないんですけどね。それで調整してやったりしていたんですけど。
──ギターを加えるというアイデアはどこから?
いや、あえてギターを加えたいというのではなく、この素材で馬場君とやってみたいということだったんです。
──そちらを優先したんですね。
というか、自分だけで遊んでいてもイマイチなんですね。
やっぱりギターが入るとサウンドの幅がボーンと広がるから、ガラッと世界が変わってやりやすくなるんです。
──ピアノとやろうという発想はなかった?
ピアノでやっちゃうと、もっとゴージャスになっちゃうんですよ。そうなると、教則本ならではのシンプルなおもしろさが薄れちゃうかなと思ったので。
練習曲って、コードも振ってないし、単旋律でしょ?
おそらくピアノの人とやるとなれば、こんなのアホらしくて弾いてられない、みたいになるんじゃないか、と(笑)。
それでゴージャスなコードを付けるようにしちゃうと、そうなりたくないというか、素朴なままのほうがいいというか、そのほうが楽しいんですよ。
だから、ギターのほうがよかった。
──ピアノだと、お茶漬けでいいって言ったのにフルコースが出てきちゃうみたいな?
そうかもしれない(笑)。
トゥー・マッチにしたくなかったんです。

♪ 練習曲を介した会話の楽しさをコロナ自粛が教えてくれた?
──コロナ禍は創作意欲にどう影響したとお考えですか?
自分を掘り下げるのにとてもいい時間でしたよね。
こんなに暇なことはなかったので、いろいろ考えることになり、それはそれでよかったのかな、と。
──新作のテーマであるエチュード(練習曲)を引っ張り出してこようというのもそのメリットのひとつだったわけですが、作曲にも影響したりしたのでしょうか?
いや、作曲とエチュードはぜんぜん関係がないと思いますね。というか、別にエチュードばかりを弾いていたわけではないので(笑)。
それに、クラシックの作曲家みたいに、すべての楽器を想定してアレンジして、というスタイルではないし……。
──浮かんだアイデアがおもしろくて、それを共演者と共有できればいいというスタイルというか……。
あ、そういうことですね。
まぁ、僕から生まれる曲は、すべて“小唄”ですからね(笑)。
ただ、それを“あの人と一緒に演奏したらどうなるかな?”みたいなイメージの膨らませ方はあるんだと思うんです。
──ということは、今回のエチュード(練習曲)をもとにした“小唄”が、ピアノ・トリオになったり、別の楽器編成になったり、オーケストラになったりすることもあると?
いや、それはまったくないです。もう、これでおしまい(笑)。
──馬場さんとのデュオでレコーディングして、これでチャンチャン、なんですね?
そうですそうです。
馬場君とは共演して作品を残しておきたかった。彼もそれをおもしろがってやってくれたので、これ以上の希望はないんですよ。
──なんか、もったいないような気もします。
だって、この譜面だと、ピアノとかほかの楽器がやろうとすれば、すごく簡単なんですよ。
もともとエチュード自体がシンプルだからね。それに対して「どうすればいい?」って共演者から疑問を投げかけられたら、僕にはどうしようもできない。
ベースのアンサンブルだとか、チェロや低音楽器のアンサンブルなら、多少の発展の余地があるかもしれませんけれどね。
──今回はハーモニーに重きを置いた作品ではないということが関係しているのでしょうか?
そう、難しいハーモニーは使っていないですね。
──ジャズならではのコード・テンションに凝るわけではなく、ただ単純に2人でメロディーを分け合って演奏して、それが楽しかったという……。
そうそう、それなんですよ。
──すぐこじつけて講釈したがる悪い癖が音楽ライターにはあるんですが(笑)、コロナの分断で言語にしろ演奏にしろ“会話のハードル”が上がったときだからこそ、一緒に楽器で会話ができることの楽しさがこの作品につながった、みたいな感じなんでしょうか?
なるほど(笑)。
馬場君はどう思っているかわからないけど、僕はそんな大層な思いでやったことではないので……。
ただ単に、やっていておもしろいなと思っただけなんですよ。
確かに、言われてみれば、ほかの低音楽器とやってもおもしろいかもしれないですね。僕はファゴットとも一緒にやったりしているから。

♪ 演奏者と観客の分断をどう解決するかが配信の課題
──今後のライヴ活動のお話をしていただこうと思っていたのですが、雲行きが怪しくて、不確かな状況が続きそうです。
そうなんですよね。このアルバム発売記念ライヴも予定しているんですが、少しようすを見てから決めようという感じになっています。
──ライヴ配信については?
うーん、僕はあんまり得意ではないので、そういう意味でも困っているんですけどね。
──どんなところが“配信はイマイチだなぁ”と思いますか?
まず、お客さんがいないのが困りますよね。なんか、レコーディングしているような気分になっちゃうんですよ。どうしてもライヴのようにはハジけることができない。そこがちょっと、抵抗が残っているかな。
嫌というわけではなくて、これまでの配信でも、音楽自体は楽しめているんですが、やっぱりリアル・ライヴのときの“お客さんとの一体感”がまったく感じられないというのがねぇ……。
いや、カメラの向こうにお客さんがいるのはわかっているんだけど。
──観客側にどんな音が出ているのかも確かめられませんよね。
そうですね。ライヴだとそれもレスポンスで伝わってくるんですけれど、それがないのがやりにくいと感じていますね。
──2021年の抱負をうかがえますか?
うーん……。
ただ単に、世の中が元に戻ってくれればいいと思うだけですね。
でも、今年だけで済むかどうかもわからない状態じゃないですか……。
音楽的になにかというより、そっちのほうがどうにかなることを願っています。
──上半期のスケジュールというのは?
いや、ぜんぜんないですよ。入れられる状態じゃないですから。
ホールとかの大きい仕事はないし、小規模のライヴが3ヵ月先ぐらいからポツポツとあるぐらい。それもどうなるかわからないですからね。
それと、地方へツアーに行かれないというのも困っています。
──ありがとうございました。またライヴのときにでもリアルにお目にかかれることを願っています。
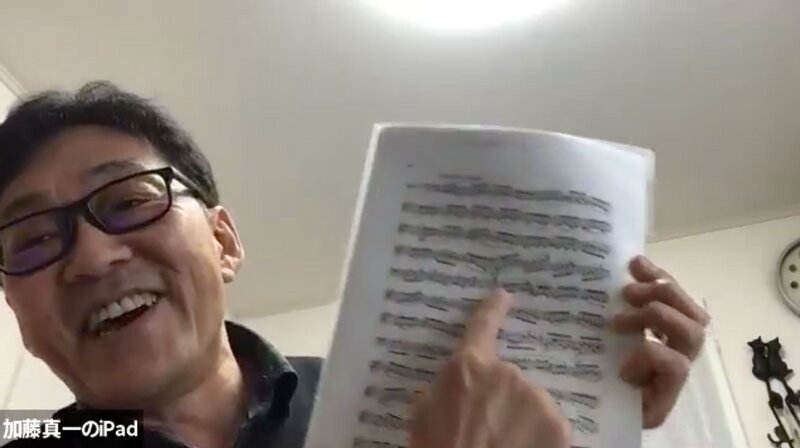
※このインタヴューは2021年2月5日にビデオ会議システムZoomによる非対面で実施しました。
Album Information

ETUDE(エチュード) / 加藤真一 & 馬場孝喜
加藤 真一 KATO Shinichi (bass)
馬場 孝喜 BABA Takayoshi (guitar)
リリース情報 http://bowz.main.jp/fsl/0020/
★Profile

加藤真一
北海道出身。1985年、猪俣猛トリオに抜擢され上京。同トリオにて全国のオーケストラ、吹奏楽団とも共演。1992年、永住権取得を機にニューヨークへ移住。マイク・スターン(g)を迎えてのリーダー・アルバム『サムシング・クローズ・トゥ・ラヴ』をリリース。1995年の帰国以降、自己のグループ(B-HOT CREATIONS)やベース・ソロを中心に、数多くのセッション、サポート活動を繰り広げる。2002年、富樫雅彦(JJ Spirits)に参加。佐藤允彦(p)とTipo CABEZA結成。2005年、佐藤允彦率いるsaifaにてメールス・ジャズ・フェスティヴァル、ノースシー・ジャズ・フェスティヴァルに出演。現在、佐藤允彦、市川秀男(p)、嶋津健一(p)らのトリオなど多数参加。美しい音色と繊細さ、重厚なリズム、ジャンルを超えた多様な演奏スタイルは、日本の音楽界に欠くことのできない存在。 https://katoshinichi.net/
馬場孝喜
京都府出身。中学時代からギターを始める。2004年、ニューヨーク〜ブラジルに渡航し、Bilinho Teixeira(g)に師事。ボサノヴァ、サンバ、ショーロなどブラジル音楽に傾倒する。2005年、ギブソン・ジャズギター・コンテスト最優秀ギタリスト賞受賞。2006年11月25日に京都コンサートホールで行なわれた「佐山雅弘 PLAYS ゴールドベルク変奏曲」第2部の佐山雅弘トリオに参加。2008年より拠点を関西から東京へ移す。佐山雅弘(p)、井上智(g)、大坂昌彦(ds)、沢田穰治(b etc.)など多数のミュージシャンと共演。現在、自身のグループやさまざまなセッション、レコーディング、講師など、幅広く活動している。
※Profileはレーベルのリリース資料より引用
★Live Information
2月22日(月)
加藤真一・馬場孝喜Duo(アルバム『ETUDE』発売記念)
出演:加藤真一(Bass)馬場孝喜(Gt)
場所:live space ZIMAGINE
東京都港区南青山6-2-13 ファイン青山B1(エレベーター有)
TEL: 03-6679-5833










