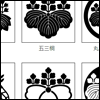五七の桐
家紋・五七の桐は現在、日本国の政府機関を象徴する紋章として使用されています。また豊臣政権の象徴としても有名ですね。では五七の桐なぜ、このように「国政執行のシンボル」となり得たのでしょうか?この家紋の成り立ち・意味や由来を時代背景と共に迫ってみます。
[五七の桐]は高級木材である桐の木の葉や花序をモチーフにした[桐紋]の一種で、普段家紋に触れる機会のない方でも、「一度は目にした事がある」という方も多いのではないでしょうか。
桃山期の国家指導者・豊臣秀吉の家紋として記憶している方や、また、総理大臣および内閣府の紋章として使用されている印象をお持ちの方が多いでしょう。これはどちらもその通りなのですが、なぜかつての太閤・秀吉の家紋が、現代日本の政府機関のいわば象徴として用いられているのでしょうか。
さらに言えば「なぜ秀吉の家紋は五七の桐だったのか」という事も含めて、五七の桐に込められた意味や由来を、当時の時代背景に合わせて詳細に解説してみたいと思います。
※家紋・五七の桐のベクターフリー素材をお探し方へ。[EPS][PDF]ファイルのダウンロードリンクはページの最後にあります。
五七の桐の誕生は、秀吉の時代からさらに昔に遡る。
五七の桐の原型は同じ桐紋種で、現代で言うところの[五三の桐]です。この[五三の桐]の起こりは、奈良時代もしくは、それより以前に仏教と共に伝来した中国のとある故事に倣って文様化(正確には桐竹鳳凰文)され、当時の上流階級に愛好されたことから始まります。
為政者が気にかけた"鳳凰"にまつわる故事とは?
この"中国のとある故事"とは、その出現が何らかの吉兆を示すとされる"瑞獣"の一つで、架空の霊鳥である[鳳凰]にまつわるものです。[鳳凰]の出現が意味する吉兆とは、『徳の高い聖天子による平安な治世の訪れ』です。
そして鳳凰がその姿を表した時、唯一その止まり木とするのは[桐の木]であるという謂れから、当時の中華圏の指導者にとって桐の木は、"神聖視"の対象でした。鳳凰の出現は、自らが『徳の高い王者』である証明ともなり、その止まり木である桐は、鳳凰が『留まり続ける』という恒久性を示すからです。
その謂れは日本の天子にも重要視された。
このような故事に基づいた文様である事から、この桐竹鳳凰文は、上流階級とはいえ、あくまで天皇の臣下に過ぎない公家衆以下の使用がはばかられるようになり、やがて天子たる天皇の文様という慣例が出来上がったと推測されます。
平安時代前期ごろに、嵯峨天皇の治世に下された詔勅により、天皇が執り行う祭祀や国事に用いる御装束は[黄櫨染の御袍=こうろぜんのごほう](現在でも即位の礼などに用いられる)に定められましたが、この御装束に用いられる文様が桐竹鳳凰文であったことから、この詔勅を以って桐紋は、正式に皇室専用の文様になったといえるでしょう。
やがてこの桐竹鳳凰の文様から、[五三の桐]の部分を紋章として取り入れるようになり、その後に作られた華美な印象を与えるこの[五七の桐]を、より上位の紋として定めたようです。
以上のような経緯から、五七の桐紋はかつて皇室専用の"やんごとない"紋章であったのですが、それがやがて秀吉のような"臣籍"の立場にある者の紋章となったのは、どのようないきさつからなのでしょうか。
※桐紋の成り立ちに関するさらに詳しい解説は↓こちらをご覧ください。
土地と人民の統治における[既存の秩序]とは?
長らく天皇家の公の紋章となっていた桐紋を、臣民が表立って使用するようになる最初のきっかけは、後醍醐天皇により足利尊氏へ[五七の桐]紋の下賜が行われたことでしたが、ではまず、このような事態へと至る"時代の転換点"に迫ってみましょう。
"武士政権の誕生"により、国家運営の仕組みが大幅に転換。
ここで言う時代の転換点とは、いわゆる源平合戦において平氏政権を打倒した、源頼朝による[武家政権]が確立された時点です。
源頼朝による武家政権の確立、すなわち鎌倉幕府の成立は、それまでの日本における"国家運営の仕組みが大幅に転換"された、日本史上の重大な画期の1つと言え、これは五七の桐の歴史にも間接的に関わって来ることになるのです。
この「国家運営の仕組みが大幅に転換」された出来事を説明するためには、古代の日本において、"土地と人民の統治がどのように行われてきたか"について、まずは触れなければなりません。
地方統治の要であった[国衙]とは?
古代の日本は、大化の改新に始まる一大政治改革により、[律令]("律"は刑罰についての規定・"令"は国家運営のための行政法の全般)の定めに則った、朝廷を中心とする中央集権的な官僚体制を成立させました。
この律令制下における大原則は、"全ての農地は国有地(公領と言う)である"と事ですが、その[公領]を地域ごとに管理・支配する[国衙=こくが]は、中央省庁(朝廷)の出先機関として、当時の日本国を運営する上で、極めて重要な存在でした。
国衙は、"武蔵"や"摂津"といった律令に定められた行政国単位で設置され、中央派遣の国司(またはその代官)の指揮の下、行政・検断・軍事・警察・徴税などの権利を行使して、その地方の土地と人民を一元管理した、現在で言うところの都道府県庁のような存在と言えば分かりやすいでしょうか。(権限は都道府県庁よりも強いですが)
しかし、時を経るにつれ顕在化していく"原則"の歪みもあり、朝廷の直接の管轄下にあったはずの国衙は、その支配を有力な個人に委ねる[知行国]という制度へと"変質"してしまいます。これは、個人が国衙の権力を通して地方を容易にコントロールできるという側面もありました。
このような知行国は[院政期]以降に爆発的に増大し、最大で律令国全体の8割近くが知行国化したとも言われています。平清盛率いる伊勢平氏も「平氏にあらずんば…」で有名なその最盛期には、一門で日本のおよそ半数の地域の知行国司を兼ねたことで知られています。
ただ、そのような変遷を経ながらも、治安や法秩序の維持・統制など、地方の統治はあくまで"国衙ありき"であったという事実に変わりはなく、何より、全国各地からの税収入の確保を司る存在として、朝廷由来の統治システムを構成する重要な要素の一つであり続けました。
律令制の"例外"でありながら、既存の秩序の形成に欠かせない[荘園]。
国衙だけではなく、律令制の"弛緩"の賜物とも言えるもう一つの歪み、[荘園]についても、当時の基本秩序を形作る重要な要素として触れておかなければなりません。
先述の通り、全ての農地は国有地であるのが律令制の原則ですが、墾田永年私財法(新たに開墾した土地なら私有を許可する法)を根拠に、地元の有力農民や中央の権力者の主導による大規模な土地開発が進み、やがて広大な私有農地(荘園と呼ばれる)が全国に乱立するようになります。
その単体のサイズが、現代で言う市町村級のスケールである事も珍しくない"荘園"ですが、そこで生活を営む人々は、国衙支配の公領に住む人々とは一線を画し、荘園開発者の支配を受ける"領民"という様相を呈してくるのです。
時代が下ると、為政者によるあからさまな利益誘導により、荘園は事実上の治外法権と化し、(徴税権を含めて)国衙の干渉を受けない"領国"のような存在となります。これが"荘園領主"たる大貴族や有力寺社、果ては皇族の重要な経済基盤となるのです。
しかしこの荘園は、実際には法的根拠の薄い脆弱な存在で、中央における権力闘争の影響や、私腹を肥やす現地国司(税の一部は国司の収入となる)の横暴により、常に収公(私有地を取り上げて公領に組み込むこと。)の危機に晒されていると言ってもいい状態でした。
"特権階級"ではない、地元の有力農民が開発を行った荘園は特にこの傾向が顕著です。そこで地方の荘園開発者は、皇族や大貴族、有力寺社に、新たに開発した土地を"寄進"することでこの事態に対処するようになりました。
これでその荘園は、差し出された側である有力者の名義に"書き換わり"ます。"有力者の領地"という形を取ることで、無法者の略奪や(末端)公権力の介入を(その権威を盾に)回避するためです。
寄進を行った開発者は、寄進された新たな荘園領主の"荘官"という形となり、荘園の現地支配や管理に従事し、そこから得られた収入のうち、事前に取り決めた割合に応じて領主に"上納"する仕組みというわけです。(実際の権利関係は、もっと複雑です。)
このような荘園の寄進は、日本国中から(特に)摂関家や皇族に集中するようになり、そこから生み出される莫大な富は、時の国家指導者の絶大な権力の源泉となった事から、先に触れた"国衙"と並んで、この"荘園"も既存の秩序を構成する上で、欠かせない重大な要素となります。
[既存の秩序]の"崩壊"によって、朝廷を中心とした統治システムの形骸化へ。
律令の制定以降、権力の変遷は[天皇親政→摂関政治→院政→平氏政権]といった流れを経てきましたが、それらはあくまで、律令制に則った既存の秩序のもとに行われてきました。しかし、平氏政権を打倒した源頼朝を中心とした東国における武士政権の誕生は、既存の秩序そのものが崩壊していく端緒といえるものでした。
平氏政権が追いつめられていった"治承・寿永の乱(いわゆる源平合戦)"の折、鎌倉を中心とした東国において(伊勢)平氏勢力を追い出し、在地武士団に対して"独自に"所領の給与や保証を行う事で、一大勢力を築き上げた源頼朝ですが、既存の秩序における枠組みの下では、それはあくまで"押領"の状態に過ぎませんでした。
そんな頼朝方の独自の権力機構(東国政権)ですが、平氏の独裁や源義仲の横暴に頭を悩ませていた後白河法皇との交渉により、[地頭]の設置・任免権を得るなど、朝廷由来の統治システムに組み込まれる形で、名目の上においてもその正統性を追認させることに成功します。ただしこれは朝廷側にして見れば、苦肉の策と言えたかもしれません。
在地武士の正体は、荘官や在庁官人たる武装有力農民。
頼朝が東国に築いた独自の地方政権は、のちに地頭となる[在地武士]の所領を、東国武士の棟梁である頼朝の権威の下に保証し、軍役などの負担を通じて応えるという、"主従関係"の上に成り立っていました。
この"在地武士"とは、元は地域の有力農民が武装した存在で、その影響力をもって切り開いた開発地を中央の有力者に寄進しては、寄進荘園の現地の荘官となって実際の経営に勤しんでいました。
また彼らは、地元の有力農民としての側面も持ち合わせているため、国司によって郡司や郷司に任命され、公領の管理や徴税代行など、国衙の業務に従事することも珍しくありませんでした。
しかし、これらの在地武士は、事実上の所領を有していながら、国司や荘園領主の支配に左右される立場であったため、既存の秩序においては、多分に不安定な存在でした。
在地武士が御家人、そして地頭へ。
これら在地武士の中で鎌倉政権に従った者は[御家人]とされ、[地頭]職に補任される事で(幕府の権威のもと)、従来の所領(自らが荘官を務める荘園など)の支配や、新たな土地の領有の正統性が補強される事になり、また後における"地方領主"としての足がかりを得る事にもなります。
この"地頭"は、鎌倉政権初期の頃には、警察権と軍事権のみを持つ存在で、国司や荘園領主の権力は依然として強力でしたが、地頭職の任免権は幕府の専権事項であったため、仮に地頭の横暴があったとしても国司や領主は、訴訟を起こす程度の対応が関の山でした。
ここでいう地頭の横暴とは主に、国衙の代官や荘園の荘官として代行した徴税分の納入を遅延・横領する行為を指します。収入の完全なストップを避けたい領主側は、領域のうちのいくらかを地頭の所有と認める代わりに、領主所有部分からの確実な上納を約束させるなどの手段を講じます。(いわゆる下地中分)
このような経緯を経るうちに、地頭による公領・荘園における権利は警察・軍事のみならず、行政や検断にまで及ぶ事となり、地方の支配権は、国衙・荘園領主から地頭へと、ゆるやかに移行していくことになります。
こうして既存秩序の崩壊は始まった。
このように、国司や荘園領主の立場が弱くなっていった要因は、地頭職をめぐる制度上の問題だけではありません。先にも述べたように、在地武士(有力農民)の土地領有の根拠は、既存の秩序のもとでは、大変に脆弱であったため、有力者への寄進を通して自らの土地を守る必要がありました。
ですが、幕府を中心とした統治体制が盤石となるのに従い、地頭職である事"それ自体"が土地領有の正統性の何よりの根拠となったため、必ずしも寄進先(荘園領主=有力貴族)の庇護を必要としなくなったという背景があります。
実態の伴わなくなった"名目上の領主"に、ご丁寧に分け前を供する必要はないという訳です。このような経緯が朝廷側の権力の喪失、既存の秩序の崩壊へとつながっていくのです。
承久の乱は朝廷政治終焉の決定打。
いずれにせよ、東国支配の正統性を朝廷側(後白河院)に認めさせた事で、武家政権が確立されますが、これは一時的な措置に終わりません。1221年、後鳥羽上皇により、王権の回復を企図したとされる"承久の乱"が引き起こされますが、上皇方は、当初の見立てを桁外れに上回るおよそ20万の幕府軍を前に、大敗を喫してしまいます。
朝廷より、幕府執権に対する追討の院宣(上皇・法皇の命令が記された発給文書)が下されるという事態に、動揺を隠し切れない御家人に対して、北条政子が夫・"源頼朝から賜ったご恩"を訴えて、結束を図った事は現代でも知られています。
そして、この事が乱を勝利に導く大きな要因として語られることも多いのですが、実際のところ、旧来の秩序が回復するよりも、幕府権力がより一層高まることの方が、武士階級にとって好都合であったという事実も見逃せません。
戦後、上皇の親衛隊たる北面・西面武士ならびに、それに与した公家および、その家礼(有力貴族と主従関係を結ぶ貴族や武士)たる西国・在京武士はことごとく処分され、上皇方の没収荘園の規模は全国3000箇所にも及び、幕府御家人の恩賞として分配給与されます。
"新恩給与"も"本領安堵"と同じく、地頭への補任を以って行われますので、この戦後処理を期に幕府の地方統治の担い手たる地頭が、東国のみならず西日本にも大量に誕生することになります(新補地頭)。
こうして幕府の権限が日本全域へ及んだ事により、日本における統治機構は、律令制に基づく朝廷由来の国政機関から、幕府が新たに構築した国政機関へと移行し、武家政権の誕生・一般化という国家運営の大幅な転換がなされたのです。
その戦後処理は皇室にも及び、朝廷の独立性も危ぶまれる事態に。
なお、後鳥羽上皇から没収された広大な皇室領は、幕府が担ぎ出した後高倉上皇へ、再編の上で返付されましたが、その膨大な規模の荘園群にもそれぞれ地頭が補任されるなど、幕府の強い影響が及ぶ結果となってしまいました。
さらに事態は、幕府の勢力が全国へと及ぶだけに留まらず、京には朝廷の監視機関(六波羅探題)が設置されるなど、朝廷および皇族は幕府の監視・管理下に置かれます。
朝廷は幕府の意向を忖度し、細大漏らさず幕府に"お伺い"を立てるようになったばかりか、朝廷上層部の専権事項であった皇位継承権にまで影響力を行使される始末で、この状況に思いを馳せるに、朝廷側が武士に対して抱いた"口惜しさ"は如何ばかりであったでしょうか。
皇族・公家衆の没落の始まり。
既存の秩序が崩壊した事で、中央官庁である朝廷・地方行政を担う国衙という旧来の統治システムを介さず、新たな秩序のもとに構築された幕府由来の統治システムが国政を主導する事になります。それは即ち、朝廷やその有力者が、土地や人民の統治権を失った事を意味します。
政治における権力闘争とは、結局のところ土地や人民の奪い合いであり、その土地や人民の統治権を失うという事は、治安や法秩序の維持を主導できない事以上に、税収入という重大な"経済基盤"を失う事を意味します。
経済力は権力の獲得・保持の源泉です。そして権力は経済力を増大する梃子となります。皇族・貴族は、これらを失うことで権力を失い、権力を失うことで、経済的な困窮すら招いていく事となります。そしてこの後、既存の秩序であった朝廷中心の統治システムは、時代を追うごとに形骸化の一途をたどる事になるのです。
皇室の紋章である五七桐が、臣民に下賜された経緯。
このような状況の中で、新たに即位した[後醍醐天皇]は、流罪に処せられても倒幕の志を貫徹し、その実現後、再び武士に実権を奪われる局面で、朝廷を二つに割ってまで抵抗するなど、武家政権を否定し、天皇の執政による治世(天皇親政)を実現させようと執念を燃やした人物でした。
五七桐の下賜は"破格の恩賞"であった。
鎌倉幕府が打倒された後、一度は後醍醐帝の宿願たる天皇親政(天皇が直接政治と行うこと)は実現します。そして、その勲功第一とされたのが[足利尊氏]で、従三位の官位と、29箇所に及ぶ領国経営権、天皇の諱(いみな=本名)「"尊"治」の偏諱(へんき=貴人の名の一文字を授かる)などとともに、[五七桐]の下賜も行われたのです。
まず、この時点における天皇の諱の一字拝領と専用紋の使用許可は"前代未聞"です。さらに後醍醐帝の治世(建武の新政)下のわずかな期間で、尊氏の位階は"従二位"に至るという急速な昇進が実現します。
事実上の国家指導者といえた鎌倉幕府の執権でさえ、その位階の上限は"正四位下"であった事を考えれば、尊氏に対するこれらの待遇は、その功に十分報いているという見方も出来ます。(ちなみに鎌倉幕府将軍の源頼朝は"正二位"で、この位階は常設官の最高位である"左大臣"に相当。)
しかし一方で、新たな支配地に加えられた恩賞給与の規模に物足りなさを感じる事も確かで、ここに「再び武士に主導権を渡すわけにはいかない」という後醍醐帝の意志がにじみ出ているのではないでしょうか。
奇跡的に訪れた既存の秩序"復権"の機会をふいにしてしまうのか。
しかし、このような後醍醐帝の姿勢は、一部を除いて末端の武士にまで影響し、恩賞の不足や不平等という形となって現れます。武士の立場に立ってみれば、鎌倉幕府の治世下と比較して状況は良くならず、倒幕のために骨を折った甲斐がないとして、建武政権に対する彼らの不満は急激に高まる事になるのです。
そして後醍醐帝の建武の治世は、武士の反感を強めるだけにとどまらず、同じ朝廷の側であるはずの公家衆の心理的な離反をも招きます。なぜなら後醍醐帝の狙いは"朝廷中心"ではなく、"自らを中心"とした政治体制を築くことだったからです。
しかもその手段は、稚拙と断じざるをえないもので、長年培われてきた「先例に則ることを重視する」という、朝廷における根本の価値観を破壊する急進的な改革を断行し、"家格の無視"を始めとした、古くからの慣例を顧みない人事などは、公家衆の大きな反発を招きます。
また、実現の可能性を考慮しない甘い見通しに立脚した(あるいは著しい理想主義に偏った)政策により、政治のさまざまな局面で大混乱が生じました。これでは、どの立場の人間であろうと、懸命に後醍醐帝を支える旨味がありません。
この時代において、"実力組織"そのものである武士をないがしろにした時点で、安定した政権運営など望むべくもありませんが、さらに公家衆の支持まで失っては、建武政権の瓦解は時間の問題でした。
加速してゆく朝廷の形骸化。
そして後醍醐帝は、足利尊氏を頭領とした武士勢力の離反により、わずか2年半で再び京を追われます。以後京をめぐり、尊氏方との攻防を繰り広げますが、最終的には光明天皇を擁立し、室町幕府の原型を築いた尊氏に対抗し、吉野に独自の政府(南朝)を樹立する事になるのです。
院政・摂関政治・武家政権を否定し、自身を中心とした政治体制の構築を追求した後醍醐帝の執念は実らず、その死後50年の時を経て南北朝は統一され、再び武士が国政を執行する事により、安定を得る世が訪れます。
この室町時代に、守護大名に新たに認められた半済令(はんぜいれい=荘園・公領の税の半分を徴収できる)により、地方行政は守護領国制へと移行します。武士による土地や人民の(貴族や武士などが入り乱れた複雑な利権構造を廃した)一元支配が強化され、皇族・公家衆のさらなる困窮の進行を促進します。
皇族以外の使用の前例から、国政執行の象徴としての慣例化への端緒。
後醍醐帝より拝領した五七桐は、足利宗家(尊氏)の覇業に付き従い、室町政権下でも管領や広域守護大名として影響力の強かった、足利一門衆(分家)である吉良氏・今川氏・細川氏・斯波氏・一色氏などの諸氏にも分け与えられます。
また、それら一門衆以外にも、室町期全般を通じて桐紋の下賜を配下武将に行うなど、その権威は政権運営にも利用されたようです。このような経緯もあって、五七桐は徐々に"国政執行を象徴する紋章"としてのイメージが根付いていく事になります。
しかし先述の通り五七桐は、そもそも"国政が委ねられた有力者に下賜された"というわけではなく、(それまでの状況を考えれば)"絵空事"とも言えた、朝廷側の復権が達成された事への破格の恩賞として実現したものです。
したがって、五七の桐を賜った足利家が、"成り行き"で国政を担った事が、結果的に国政を委任された有力者の使用する紋章としての"前例"となったに過ぎません。
ここまで見てきたように、武士に国政の実権が移り、朝廷が影響力を喪失していくという、この一連の経緯がなければ、五七桐の臣民階級への下賜の実現もありませんでしたし、さらに足利治世下となり、朝廷の形骸化が加速しなければ、"国政委任"のシンボルとしてのイメージが根付くこともなかったでしょう。
いずれにせよこの事が、皇族以外の者が表立って五七桐を使用できる端緒となり、豊臣秀吉や日本政府の使用へと繋がっていくのです。
委任統治者の紋としての慣例化。
室町幕府が滅亡し、織田信長が本能寺で討たれると、次に豊臣秀吉の治世が訪れます。信長の死後、秀吉が、後継に名乗りを上げた有力者たちとの権力闘争を勝ち抜く最中、関白就任・豊臣への改姓と太政大臣への任官を経る中で、後陽成天皇より"桐紋"と"菊紋"の下賜が行われたといいます。
桐紋を正式に使用する権利を得た秀吉は、まず自らの衣服や調度にとどまらず、城建物の外装にまで桐紋を用い始めます。
また、自らの所有物に限らず、秀吉によって造営・再建された寺社の装飾、また"天正長大判"や"大仏大判"といった秀吉期の貨幣など、人目に触れるところ、言わば公的なものにも惜しみなく桐紋を使用しました。
さらには自らの配下武将に、"豊臣"や"羽柴"の氏姓と共に、"五七"や"五三"を始めとした、様々な桐紋の賜与を行います。
清和源氏の名門家系である足利氏はもちろん、名門とは言えずとも重代に渡り組織された、譜代の家臣団を擁していた信長や家康とは違い、出自に特段のアドバンテージのない秀吉は、このように朝廷由来の権威を大いに利用したのです。
再び日の目を見て現代に至る。
江戸時代の末期には欧米列強の軍事・経済的圧力により、大政(国政)を担うべき幕府の施策は迷走し、その権威は大きく失墜します。そこで開明派の諸勢力は連合して天皇を担ぎ上げ、新政府を樹立しました。新政府主導の"御一新"(明治維新)により、ついに日本は近代化を迎えます。
しかし、新たに誕生した明治政府は、立場も地域もバラバラの"寄り合い所帯"な上に、戊辰戦争の真っ只中という非常に不安定な状態で始動することを余儀なくされ、そしてその懸念は早くも表面化してしまいます。
公家と武家、さらに地域によって、日本における従来の正礼装は形・色・柄のすべてにおいて不揃いで、いざ大きな国事が催されると、そのあまりの統一感のなさに国内外において、大いに面目を失したと言います。
これは政府のみならず、民族そのものの文化的な"格"が問われる問題でもありました。そこで政府は、諸外国に開けた新たな日本国にふさわしい、格調高い正礼装を含む、日本国公式の統一された服制を整えるべく、西洋式の装いに範を求めました。
現在の正礼装である"燕尾服"や"モーニング"を準礼・略礼装扱いとして取り入れ、その上の正礼装に、西洋でも当時、最上級の装いであった宮廷制服を模した[大礼服]が定められるのですが、この最上級の礼装にあしらうべく、日本政府を象徴する文様として選ばれたのが、この五色の桐だったのです。
幕藩体制からの大転換を図った、天皇を君主とする新体制の発足を印象づける意味でも、これまで"国政執行"の象徴として十分な"実績"を挙げてきた五七の桐を、明治新政府の紋章とするのは、さまざまな状況を鑑みても、ごく自然な判断だったのかもしれません。
これ以外にも五七の桐は、正式な定めではなくあくまで慣例的とはいえ、実質的に明治以降の日本国政府の象徴として、あらゆる場面で用いられ、その役割を果すことになります。
例えば、明治初期に制定された勲章制度などは、そのうちの"旭日章"の各等級のデザインの一部、または全てに桐紋が用いられました。その後、統廃合された現行制度でも、旭日章のほか、新たな分類として桐花章が定められ、桐のデザインが引き続いて用いられています。
その他、外国の賓客の接遇のための晩餐会等の招待状や食器にも刻印されるなど、対外的に政府を示すマークとしてや、また、パスポートに用いられたり、内閣府や日本政府の会見の演台のプレートとして用いられたりといった、政府機関やまた日本国そのものを象徴する紋章として利用されています。
以上が家紋・五七桐の解説でした。その他「桐紋」の一覧ページは↓こちらから。
その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。
家紋・五七の桐のフリー画像素材について
[家紋素材の発光大王堂]は、家紋のepsフリー素材サイトです。以下のリンクからデータをダウンロードして頂けます。家紋のフリー画像を探しているけど、EPS・PDFの意味がよくわからない方は、ページ上部の画像をダウロードしてご利用下さい。背景透過で100万画素程度の画質はあります。

※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。