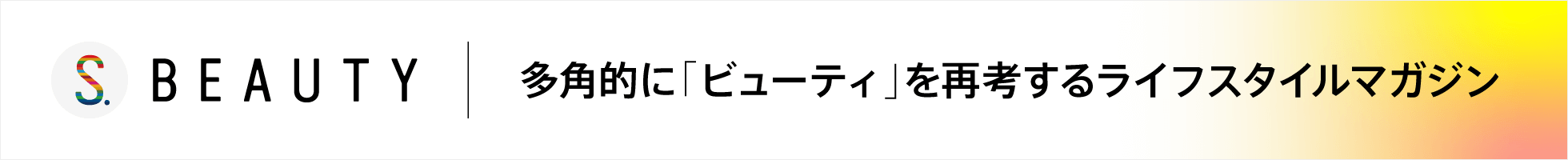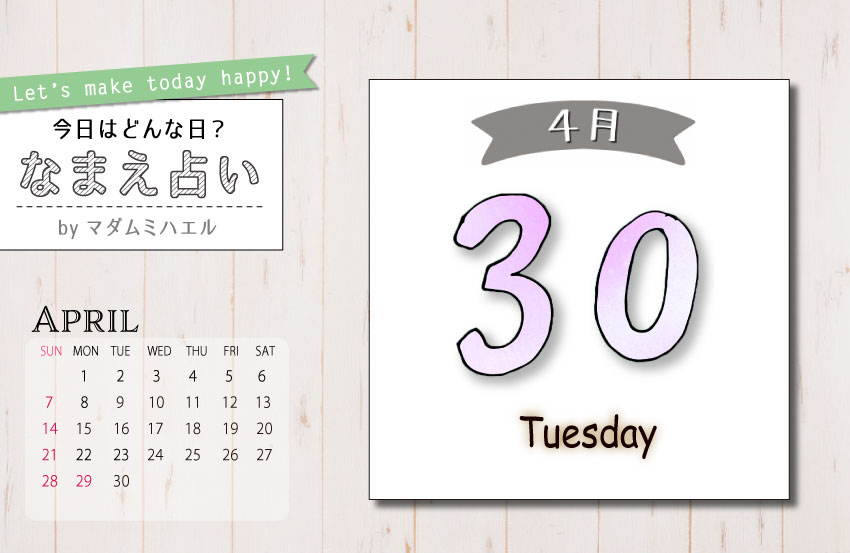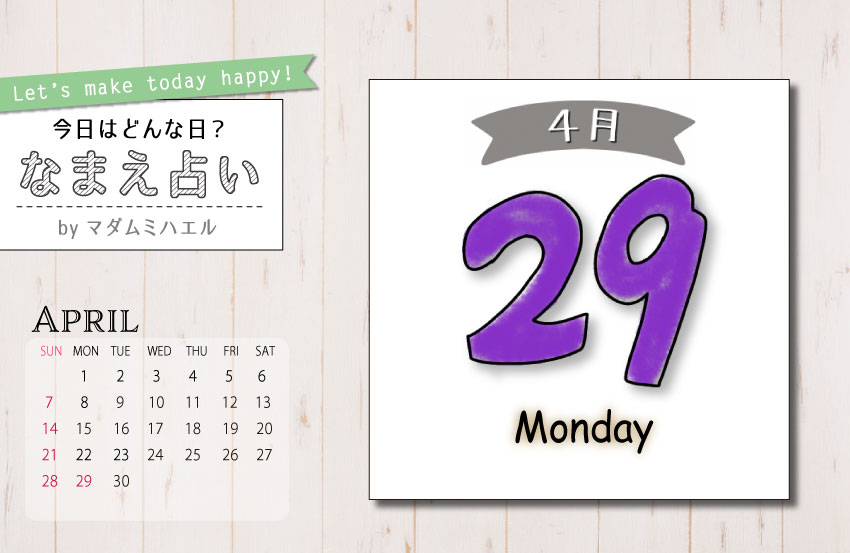「無理にわかり合おうとする時代」が生きづらかった
「天空」という意味を持つタイトルの舞台が、今日から幕を開ける。
「ザ・ウェルキン」(THE WELKIN)は、英語の古語から派生した、文語や詩に用いられる言葉である。物語の舞台は、1759年、イギリス東部の田舎町。人々が75年に一度天空に舞い戻ってくるという大彗星を待ちわびる中、少女サリーが殺人罪で絞首刑を宣告された。
妊娠している罪人は死刑を逃れることができる時代に、サリーは妊娠を主張。その真偽を判定するため、妊娠経験のある12人の主婦たちが、陪審員として集められた。サリーは本当に妊娠しているのか。それとも死刑から逃れようと嘘をついているのか。残酷なほど正直に、女たちは自分自身と少女の運命に向き合っていく――。女性たちによる陪審員審理の中で、現代の女性たちに未だにのしかかる苦難も浮き彫りになるという、英国の若手作家ルーシー・カークウッドの意欲作だ。
峯村さんはこの舞台で、陪審員の一人で、以前ロンドンに住んでいたエマ・ジェンキンスを演じる。現代日本に暮らす私たちは、「ザ・ウェルキン」の時代に比べたら、ずいぶん生きやすくなっているはず。とはいえ、どんな時代にも生きづらさがあるのも事実。作品のテーマとも重ねながら、峯村さんにとっての「生きづらさ」とそれを克服した経緯について話を聞いた。
「もちろん、まだまだ世の中は男性が作ったルールが支配しているなとは感じます。でも、私は、女性ならではの生きづらさを感じているかというとそうでもなくて。“生きづらいな”と感じることは、男性も女性も、そんなに変わらないと思うんです。私は、むしろ同性同士にも感覚が違う人はいっぱいいるのに、それを無理にわかり合おうと思っていた時代が、とても生きづらかったですね」
子供の頃は、目立つことが恥ずかしかった
今でこそ、名バイプレヤーとして多くの作品に出演し、ツイッターでも日常を呟いたりしている峯村さんだが、子供の頃は、とても引っ込み思案だった。
 撮影/張溢文
撮影/張溢文
「前へ前へって出る方では全然なくて。よく覚えているのが、小学校の登り棒にみんなで「よーい、ドン」ってのぼったときに、当時から私は背が高かったので、すごく速く登ってしまって。下で見ている子たちから、『すごい、一番だよ、りえちゃん!』って言われた瞬間に恥ずかしくなって、登り棒の途中で固まっちゃったことがあるんです(苦笑)。それで、結局みんなに抜かされてしまった。そのくらい、目立つことが恥ずかしかった」
そんな、内弁慶な峯村さんだが、思春期に入ると「自分をよく見せたい」という自意識が湧き上がってきた。
「自分をよく見せたいと思うと、人との視線の間に摩擦が生じてしまって、つらくなる。だから、10代の私は、すごく無口で、人前で喋るのが本当に苦手でした。それが、高校を卒業して、お芝居に出会ったことで、徐々に変わっていったんです。お芝居って、ちゃんとセリフが用意されているじゃないですか。お芝居を始めた最初の頃は、セリフを通して、自分の気持ちを言えるっていうことが、すごく気持ちよくて。
そうやってだんだん喋ることに抵抗がなくなってくると、今度は、セリフじゃない言葉で人と話せるようになった。『あ、喋るって楽しいんだな』と思えるようになりました。だから、お芝居は、内省的になってしまいがちな私にとっては、セラピーみたいな感じでしたね」