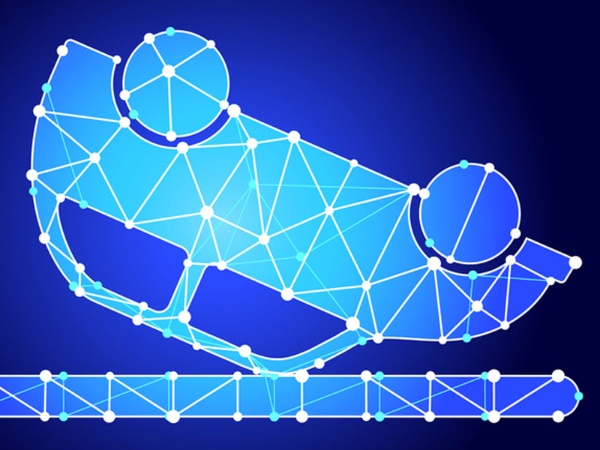4月15、16日(米国時間)、米ワシントンで第1回の日米貿易協議が行われた。来週予定されている日米首脳会談を控え、いよいよ両国が、交渉の第一歩を踏み出した。
そもそも中国、欧州との協議でフル稼働しているライトハイザー米通商代表だが、彼の日本との交渉方針は定まっていない。米国においては元来、通商権限を有するのは米国議会である。その米国議会は医薬品業界、IT業界などさまざまな業界の声をバックに、政府の交渉に公聴会などで注文を付ける。今回もグラスリー上院財政委員長などからの要求で、サービス分野などに交渉項目が広がる国内政治力学が働いている。
他方、トランプ政権側は大統領選に向けてあくまで早期の成果に力点がある。ライトハイザー代表が議会の意向もくみ取りながら、今後どういう方針で交渉に臨むかも定かではない。茂木経済財政・再生大臣にとってがそれを見極めるのが今回の主眼だった。
議会をはじめ米国の関心は明らかに中国であるが、米中貿易交渉も依然として合意に至らない。米・欧州連合(EU)交渉も農産物を交渉対象とするかどうかで折り合いがつかず、交渉の土俵作りで難航している。米欧の航空機大手に対する補助金を巡る通商問題で両者の関係は悪化するばかりだ。
そうした中、「日本は成果を出しやすい交渉相手」と米国から見られていても不思議ではない。トランプ大統領の性格からは、米朝交渉で拉致問題に言及したことも、ある種の“貸し”としているのだろう。
いずれにせよ、4月、5月、6月と、この3カ月の間に立て続けに日米首脳会談が予定されている。トランプ大統領は2020年の大統領再選に向けて支持層にアピールするための“成果”を求めてくることは間違いない。
しかし、だからと言って、「日本もこの間に早期に合意を目指すべきだ」という論は当たらない。こうした論がすぐに出て来るのが日本らしいところではあるが、それが相手国から「成果を出しやすい交渉相手」と見られるゆえんでもある。
焦っているのは米国だ
焦っているのは米国であることは忘れてはならない。米国抜きの環太平洋経済連携協定(TPP11)、日欧経済連携協定(日欧EPA)が発効した結果、牛肉、豚肉などの対日輸出で他国に比べて相対的に米国が競争上不利になってしまった。中国の報復関税によっても米国の畜産業界は打撃を被っている。
米国中西部の畜産業界の不満は高まっており、2020年の大統領選において激戦地域であるだけに、トランプ大統領にとっては早急に不満解消をしておきたいところだ。米国農業団体、農務大臣が長期にわたる交渉を嫌い、「早期の収穫(アーリー・ハーベスト)」を求めている理由はそこにある。
米国農務長官は「TPPの合意水準以上の譲歩を日本に求める」と発言し、日本も身構え、メディアもそこに注目していた。しかし、このような発言は単なる交渉術で、真に受ける必要はさらさらない。米国にとって兎も角不利な状況を解消するのが焦眉の急で、TPPでの合意水準以上の譲歩を日本に強く求めることはないと見てよい。
サービスを交渉対象とするかどうかは本質ではない
サービス分野が交渉対象になるかどうかにメディアが注目している。対象が物品だけだと自由貿易協定(FTA)ではないが、対象を広げてサービスを含めるとFTAになるといった誤解がまん延しているからだ。いまだ一部メディアは物品貿易協定(TAG)交渉という大本営発表の名称に引きずられている。
FTAという言葉を避けたい日本政府が使った言葉だが、米国はそんな言葉は使っていない。実態を見ればFTA交渉であることは明らかだからだ。
日本政府は「これまで締結してきた、包括的なFTAではない」と説明したが、「FTAではない」とは一言も言っていない。「包括的でないFTA」も当然あるのだ。しかし、メディアは誤解したまま報道している。その結果、交渉対象にサービスが含まれるかどうかが最大の課題かのように報道しているのだ。
以前にも指摘したが、物品の関税引き下げだけでもFTAであることは通商のルールでは明らかだ。逆にFTAでなければ、特定国に対して物品の関税を引き下げられないのだ(参照:日本に巣くう、強烈な「FTAアレルギー」)。
日本政府はあえてメディアの誤解を放置して、少なくとも夏の参議院選挙まではFTAという言葉を使わない方針でいるようだ。こうした呼称で実態を糊塗しようとする対応を米国政府関係者も冷ややかに見ている。実態はFTAであることは明らかで、呼称は本質的な問題ではなく、日本の国内問題だ、との立場だ。
いずれにしても日本のメディアも、「過ちては改むるにはばかることなかれ」だ。
突如浮上してきた「デジタル貿易」の裏事情
今回の会談の結果、今後の交渉で自動車、農産物といった物品だけでなく、デジタル貿易を扱うこととなった。なぜ、突如、デジタル貿易が浮上したのだろうか。
デジタル貿易とは電子商取引など国境を越えたデータの流通を意味する。米国側から「日米が(国際的に)進んでおり日米の考えに違いがない分野だ」として、交渉対象に含めるよう提案があったという。グーグルなど米巨大IT企業が海外展開しやすいよう、国境を越えたデータ移動の自由を確保したい。
実は、これは日米の国内事情からくる「3つの要求」を満たす案として急浮上してきた。
第1は、米国議会の要求を多少なりとも汲んでいる姿勢を示すことだ。物品だけではなく、広く産業界の要望を反映した交渉対象になっているという、象徴的な実例が一つでも欲しい。
第2に、トランプ政権は大統領再選に向けて早期の成果が欲しい。そのためには交渉が長引きそうなものは避けて、合意し易い分野にしたい。幸い、デジタル貿易のルール作りは日本も主導して、既に日米欧が核となった国際的な議論が相当進展している。この果実を取り込めばよいのだ。日本は米欧の間を取り持つものの、日米での意見の隔たりは大きくない。
第3に、日本政府としてはサービス分野の自由化は“無用のFTA論”を呼び起こしかねないので、できれば避けたい。デジタル貿易はルール作りであることで、その懸念は薄まる。
こうして、「デジタル貿易」はこれらの要求を満たすものとして急浮上した。しかもデータの囲い込みをする中国に対して日米が協力して牽制をするといった戦略的な意味もある。
私もかつて日米での貿易協定をするならば、TPP以降の国際状況も踏まえた「ルール」も含めて、単なるFTAにとどまらず、経済連携協定(EPA)を目指すべきと主張していたが、まさにその方向に一歩踏み出したようだ。
“つまみ食い”“いいとこ取り”ができない
今回の会談での明確になった重要なポイントがある。茂木大臣はこう語っている。
「貿易協定というものは、個別に決めるのではなくて、パッケージ合意ですから、全体が決まって合意になるわけでありまして、ここだけ決まりましたよと、これが合意ですというやり方は交渉ではとらない。これが交渉では一般的だと思います」「win-winとなるような交渉を進めたい」
実はこれが非常に意味を持っている。
交渉の本質は、サービスを含むかどうかではない。物品だけであっても、国際ルールに従った交渉にしなければならない。ポイントは2点ある。
第1に、特定国への関税引き下げは、「実質的にすべての貿易」について関税撤廃するものでなければできない。それが世界貿易機関(WTO)協定上のルールだ。米国に対して日本の農産物だけ関税引き下げするといった“つまみ食い”は許されないのだ。
第2に、関税交渉はギブ・アンド・テークだということだ。一方的に米国の要求だけを交渉するのではなく、日本も米国に対して要求して双方向の交渉でなければならない。茂木大臣の言うところの「win-win」はギブ・アンド・テイクと言い換えてもいい。
かつてTPP交渉でも関税引き下げについては2国間での交渉の集積だが、日米間では、日本の農産物の引き下げと米国の自動車関税の引き下げがパッケージで合意されたことを忘れてはならない。これは当時、甘利大臣(当時)が難交渉の末、妥結した成果である。従って日本の農産物の関税引き下げだけの“いいとこ取り”はあり得ないのだ。
米国も日本に対して相応の対価を差し出さなければならない。
まず交渉の入り口でこうした国際的に当たり前の原則・ルールを明確にしておくことは当然で、茂木大臣も交渉者として当然すべきことをしたのだろう。
自動車関税は抜けない刀の“空脅し”
日米協議の最大のテーマは自動車だ。昨年9月の日米首脳会談の共同声明ではっきり書きこまれたのが、「米国の関心は、米国国内の自動車産業の生産と雇用の増加である」ことだ。そのために、自動車の高関税を脅しに、米国が日本を追い込みたいのが、対米輸出の「数量規制」である。
この数量規制の問題の深刻さについては、拙稿「日米通商交渉の主戦場『自動車の数量規制』はなぜ“毒まんじゅう”か」で詳述したので、ここでは繰り返さない。
日本の中には、トランプ大統領による25%の自動車関税の引き上げを回避することが最重要課題であるので、早期に妥結した方がよいと主張する向きもある。これはとんでもない見当違いだ。自動車関税の引き上げの脅しは「抜けない刀」で“空脅し”だからだ。
仮に自動車関税を引き上げれば、経済への打撃が大きく、株価暴落の引き金を引きかねない。輸入車だけでなく、米国国産車の価格も上昇し、消費が冷え込むことが予想され、シンクタンクの試算では米国の雇用も150万人減るとの試算もある。大統領再選に向けてトランプ大統領が重視するのが株価である限り、採れない選択だ。ちなみに、米国議会も反対している。
「ビッグスリーよりも中西部」、かつての自動車交渉との根本的違い
これに関連して、かつての自動車交渉との根本的違いも大事だ。
かつては米国政府は米国の自動車メーカー・ビッグスリーの要求を背景にその利益のために交渉していた。そこで日本も米国政府だけでなく、裏でビッグスリーと接触することも交渉上必要不可欠であった。
ところがトランプ政権の関心は、米国の自動車産業にあるのではない。むしろ米国内の工場閉鎖に傾くビッグスリーとは対立している。トランプ大統領の関心は大統領選挙のための中西部対策にある。
従って日本としては、中西部への自動車メーカーの投資拡大で、生産と雇用の増加にいかに貢献できるかをアピールすることに解を求めることとなる。政府は民間の投資にコミットできないが、各社の投資計画をいかに繰り返しアピールし、トランプ大統領の頭に刷り込むかにかかっている。
為替条項は徹底抗戦か? 内容次第か?
通貨安誘導を防ぐための為替条項については、日米の財務大臣どうしでの話し合いでということになったようだ。これは財務省の意向を受けてのことだ。ムニューシン米財務長官は、日本との交渉では為替条項を求める考えを明らかにした。米国は先般、メキシコとカナダとの間で締結した「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」において、為替条項を導入しているが、これが念頭にある。
日本は2011年以来、円売り介入をしていないが、金融緩和も円安誘導と捉えられて金融政策の自由度が狭まるとの懸念も指摘されている。本当にそうだろうか。
この為替条項の中身を見ると、競争的な通貨切り下げを禁止し、ある国が相手国に通貨安誘導の疑いがあると判断した場合、まず両国で協議を行い、もし解決に至らない場合は、国際通貨基金(IMF)に調査を依頼する。つまり、通貨安誘導の疑いが生じただけで、直ちに制裁関税が発動されるというような、強制力のある内容にはなっていない。
実はIMF協定では、「為替の安定を促進し、加盟国間の秩序ある為替取引を維持し、競争的な通貨切り下げを回避すること」が規定されている。そのため、多くの専門家の間では、USMCAにおける為替条項は、基本的にはこのIMF協定の範囲内と受け止められている。仮に日米交渉において為替条項が導入されても、USMCAの為替条項と同程度のものであれば、日本にとってどこまで脅威なのか内容を突っ込んで見る必要があるようだ。
そもそも日本の通貨当局は伝統的に、「為替問題への対応は通貨当局間が話し合うもの」という原理原則を堅守し、これまでも徹頭徹尾、通商交渉とは切り離すことに腐心してきた。いわば、神聖な「通貨」の世界に「通商」という汚らわしいものを持ち込ませない、というものだ。この原理原則が崩されようとしているだけに、抵抗は相当なものだ。
今回、財務大臣同士という場に引き戻したので、取りあえずホッとしているだろう。しかし、これで終わったわけではない。実害があるかどうかは中身次第という姿勢に転換する必要がいずれ出てくるのではないだろうか。
夏の参議院選挙後が当面のターゲットか
まずは順調にスタートを切った今回の会談だ。今後は日米に国内政治日程が大事になってくる。
米国は秋からは事実上大統領選モードになる。トランプ大統領としてはそこに向けた成果が必要になる。他方、日本は7月に参議院選挙がある。それまでは農産物の関税引き下げやFTA論でガタガタさせたくない。
恐らく7月の参議院選挙後に一つの節目を迎えるだろう。
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。
この記事はシリーズ「細川昌彦の「深層・世界のパワーゲーム」」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。