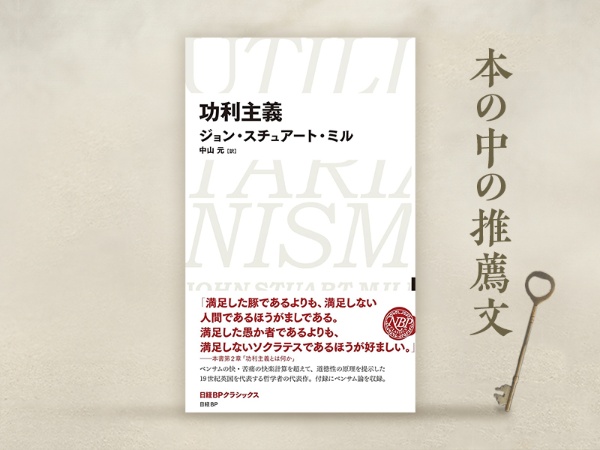「満足した豚であるよりも、満足しない人間であるほうがましである。満足した愚か者であるよりも、満足しないソクラテスであるほうが好ましい」。かつて東京大学の卒業式の総長式辞で引用され、話題となった警句が収録されたジョン・スチュアート・ミルの『 功利主義 』。日経BPクラシックスシリーズに加わった本書の「解説」として、翻訳を手掛けた中山元氏の「訳者あとがき」をお届けします。
【訳者あとがき】ミル『功利主義』の果たした役割
本書には、ジェレミー・ベンサム(一七四八~一八三二)のあとを継いで功利主義の理論を普及させたジョン・スチュアート・ミル(一八〇六~一八七三)の著作『功利主義』と、ミルがベンサムの思想の長所と短所を鋭く描き出した論文「ベンサム論」を収録した。底本としたのは、The Collected WorksofJohnStuart Mill, Volume X-EssaysonEthics, Religion,andSociety,Routledge, 1996である。
ミルの父親は同じくイギリスの著名な思想家であったジェームズ・ミル(一七七八~一八三六)であるが、父親のジェームズはベンサムと親交があり、功利主義の思想に強く共感していた。ミルは父親から英才教育を受けた。学校に通うことなく、幼い頃からギリシア語を学ばされ、経済学のリカードの書物を読まされた。毎朝の散歩の際には前日の読書の内容について報告させられ、父親の鋭い質問に答えさせられたのだった。これは学問というものを、記憶する知識としてではなく、思考する道筋をみいだす営みとさせるために父親が息子のために考え出したスパルタ教育の方法だった。
ミルはこのようにして父親から思考の道筋を示唆され、みずからノートをとりながらさまざまな著作を読み込むうちに、ベンサムの思想に魅了された。ミルは後に『自伝』において、ベンサムの思想のうちでとくに魅惑された点について、当時の道徳論の批判と、細分化による科学的な分類方法にあったと語っている。ベンサムの道徳論の批判を読んだミルは、「これで今まで道徳を説いた人たちはことごとく一掃された。ここにこそ思想の新時代が始まったのだ、という気持ちが強く来た(*1)」と熱く語っている。
またベンサムの分類方法を学んで、「わたしは何だか高いところに連れてゆかれて、そこから精神の広い領土が見わたせ、どうにも数えきれないほどの無数の小さな知的結果までが遠くのほうにはてしなくひろがっているのが見える思いがした。さらに読み進むと、この知的明晰さに加えて、人間社会の実際的改革という実にワクワクする望みまでが現れた(*2)」と力をこめて語っている。
この社会の改革の展望に鼓舞されて、ミルは友人たちと功利主義の思想を喧伝する「功利主義協会」を設立した。ミルが本書の三二ページの原注で語っているように、功利主義という言葉を普及させて、ベンサムの思想を「功利主義」という名目のもとにまとめて世間に打ち出したのはミルだった。ベンサムの著作は文体が読みにくく、ページ数も多いものがあったので、なかなか読者には手に取りにくいものだった。ミルのこの書物は人々にベンサムの思想の概略を理解するための重要な導き手となったのだった。功利主義が哲学の思想としての地位を確立する上では、ミルによるベンサムの思想の案内が大きな役割を果たしたのだった。
ミルはやがて社会改革の展望のもとで、ベンサムが中心となった哲学急進主義の運動にも活発に参加するようになった。しかしある時期からミルはベンサムへの心酔から醒めたかのように、ベンサムの思想に疑問を抱くようになった。これはベンサムの思想を教え込んだ父親の影響から自立するための苦しい思想的な営みだったと考えることもできるだろう。やがてフランスのサンシモン派の哲学者やオーギュスト・コントの思想に共感するようになった。そして一八三二年のベンサムの死去と一八三六年の父親のジェームズの死の後には、ベンサムを公然と批判するようになったが、急進派の哲学からベンサムの思想の不都合な影響を取り除いた新しい急進主義の運動を展開するようになったのだった。
本書に掲載した『功利主義』の論文は、一八六一年に『フレーザーズ・マガジン』誌に分載されて、一八六三年に著作として発表されたものである。この論文はベンサムの思想を功利主義という観点から巧みに要約したものであり、ベンサムの著作では明確に語られていなかったところまで掘り下げて検討し、部分的にはベンサムの功利主義の思想を補足して、その欠点を是正することを試みたものである。
この論文がベンサムの思想に加えた「補足」と修正は、大きく分けて三つに集約することができるだろう。まずベンサムの思想において示された快楽計算の要素を薄めて、快楽よりも幸福に重点を置いたことである。ベンサムは功利の原理について、「人間が苦痛と快という二人の主人によって支配されていること(*3)」と説明している。人間のすべての行動は、苦痛を回避し、快楽を求めるという原理によって支配されており、こうした原理によって説明できると考えていた。そしてすべての法は、この原理に適うように定める必要があり、そのためには法によって影響をうけるすべての人々の快の合計と苦痛の合計を計算して、それが差し引きでプラスになるようにすべきだと考えたのである。
この快楽計算にはさまざまな問題があり、多くの議論を引き起こしていた。そこでミルは、エピクロス哲学の流れを汲むこうした快楽主義の傾向を薄めて、快楽を幸福と言い換えたのだった。哲学の伝統においても快楽を人生の目的とするエピクロスの快楽主義の哲学には批判が多かったので、人生の目的は幸福であるとするアリストテレスの伝統に掉さすことにしたのである。そしてベンサムも採用していた最大幸福の概念を功利主義の基準として明確に定めたのだった。それによって「〈功利〉すなわち〈最大幸福の原理〉を道徳の基礎とみなす」(本書三三ページ。以下本書からの引用はページ数だけを示す)ことを明確にしたのである。この考えによると、「正しい行為とは、幸福を増進する傾向をそなえているもののことであり、不正な行為とは、幸福ではないものを生み出す行為のことである」(同)のである。
ただしベンサムもほとんど同じことを語っているので、これはミルの独創ではない。ベンサムは「功利性の原理とは、その利益が問題とされている人々の幸福を増進するか、低減させる傾向があると思われるあらゆる行為を是認するか、否認するために使われる原理である(*4)」と語っているからである。ただしベンサムは主著の『道徳および立法の諸原理』においては幸福という概念をほとんど使わず、快と苦痛の概念だけで議論を進めている。それにたいしてミルは快と苦痛の概念ではなく、幸福の概念を正面にだすことで、人生の目的は幸福になることであるという哲学の主流の伝統に依拠することができたのである。
第二に、このように幸福という概念を軸とすることによって、快と苦痛には人間を幸福にする種類のものと、人間をそれほど幸福にしない種類のものがあることを強調することができた。これは快と苦痛の総量を重視するベンサムの理論と離れて、快と苦痛の質を重視する方針を打ち出したことを意味する。それが豚とソクラテスの有名な譬え話である。ミルは快と苦痛には、動物的な種類のものと人間的な種類のものがあると主張した。ベンサムの議論では、立法においては人間全体の快を差し引きして増進させることを目指すべきであるとされていた。この場合には快と苦痛は純粋に数量化されているので、ある法的な措置によって、ごく卑俗で身体的な快楽が高級で知的な快楽よりも合計すると人類全体の快を増進するのであれば、その法は是認されることになるだろう。
しかしミルはこのような量的な快楽計算の議論を避けて、快楽にも質的な違いがあることを強調する。そして知的で高級な快楽は、人間にとって望ましい幸福をもたらすものであり、低俗で身体的な快楽よりも望ましい場合があることを指摘する。「満足した豚であるよりも、満足しない人間であるほうがましである。満足した愚か者であるよりも、満足しないソクラテスであるほうが好ましい」(四一ページ)と主張するのである。そしてこのような快楽の質的な違いのために高級な快楽は、「比較の際に量の問題をほとんど無視できるように優れていることになる」(三七〜三八ページ)ことが指摘される。さらに高級な快楽を尊ぶような人は世界全体に利益をもたらすということで、この比較の意味が明らかにされる。「だからこそ高貴な性格が世の中で善なるものとして育まれることによって、初めて功利主義が実現できるようになる」(四六ページ)と結論されるのである。
このように快楽の質の違いを重視するということは、このような高級な快楽を求める人々の存在を容認することによって、社会全体の幸福が高まることを期待するということであるが、それだけではなく、このような人々の欲望を積極的に是認することにおいて、社会のうちでの自由を促進することを期待するという意味もそなえていた。こうした高級な快楽を追求するのは例外的な人々かもしれないが、社会における個人の多様性と自由とを保護するために、「例外的な個人が大衆とは異なる行動をとる場合に、これを阻害しないでむしろ鼓舞せねばならない(*5)」と考えたのである。
こうした人々の高級な快楽を追求する自由を認めることによって、そうした人々が幸福に感じるのであれば、低級な快楽だけを是認するよりも、社会全体の快楽の度合いが低下するとしても、社会全体の自由度を高めることができるはずである。「人類は、自分にとって幸福に思われるような生活をたがいに許すほうが、他の人々が幸福と感ずるような生活を各人に強いるときよりも、得るところが一層多いのである(*6)」と言えるからである。
ミルが『自由論』で断言したように、「自由の名に値する唯一の自由は、われわれが他人の幸福を奪い取ろうとせず、また幸福を得ようとする他人の努力を阻害しないかぎり、われわれは自分自身の幸福を自分自身の方法において追求する自由である(*7)」はずだからだ。
この「功利主義」の第三の補足点は、ミルがこの論文において、ベンサムの快楽計算とは明確に異なる道徳性の原理を提示したことである。それは主として第5章「正義と功利の関係について」において語られている。ベンサムの快楽計算の理論によると、社会の全体の快楽を増進させる法的な措置は「正しい」ものであることが主張されていた。ということは、功利の原理に適った行為はすべて「正しい」すなわち正義であるということである。しかし世間一般の考え方では、たとえ快楽を損なうものだとしても、正義に適うためにはなさねばならないことがあるとされている。その場合には正義は、功利の原理に反するものとなり、幸福の増進という目標に反するものとなることになる。
これはベンサムの問題であるよりも、ミルの道徳と倫理の問題である。ベンサムがとくに問題とすることのなかったこの問題を、ミルはこの第5章で集中的に考察する。この正義の問題にたいしてミルは、イギリスのヒュームやスミス以来の伝統である共感の理論からアプローチする。正義とは何かについて、ベンサムであれば社会全体の快楽を増進する措置であると答えるだろうが、ミルはまず社会において正義はどのようなものとして捉えられているかという正義の現象学的な考察から始める。そして一般に正義とはどのようなものとして考えられているかを列挙するのである。「そこで人間のさまざまな行動様式や仕組みのうちで、人々が一般的に、あるいは広く共有された意見によって、「正義」や「不正」とみなしているものについて順に調べてみることにしよう」(一四八ページ)というわけである。
まず他人の所有物を奪うのは正義に反するとされている。これはアリストテレス以来の正義の「匡正的な正義」と呼ばれた考え方であり、正当な所有物を奪われた者はその剥奪を補われるのが正義であるという考え方である。あるいは自分に相応なものを獲得するのが正義とされている。これもアリストテレスによって「分配的な正義」という概念で提起されてきた伝統的な正義の理論である。さらに他者の信頼を裏切らないこと、すべての人に公平であり、すべての人を平等に扱うことなども、正義の一般的な概念として挙げられている。
ただしこのようにして考えられた正義と不正の概念は、そのままで法的な規制に結びつくとは考えられていない。というのも正義と不正の観念には道徳性の理論が含まれているからである。ミルは、「正義とか不正という考え方の根底に、このように罰せられるべきであるかどうかという考え方があるのは間違いのないことである。ある行為をする人を罰すべきであるとわたしたちが考えるならば、そのような行為を不正と呼ぶのであり、罰するほどではないと考えるならば、そうした行為について嫌悪や非難を示す言葉を使う」(一六六ページ)と指摘する。このように、正義と不正の概念の背後には、ある不適切な行為にたいして処罰すべきであるという道徳的な感情が存在しているのである。
そしてこの道徳的な感情は、たんに自己の防衛と自己の快楽の獲得という目的を守るという自己本位的なものではなく、社会においてともに生きる人々にたいする共感の感情に依拠していると考えられる。自分に関係のない行為でも、人々は不正には憤るものだからである。「ある個人に害を加えた人物は罰すべきであるという願望は、次の二つの感情、すなわち自己防衛の衝動と共感の感情から自然に生まれるのであり、どちらもきわめて自然な感情であって、本能的なものか、本能に似たものである」(一七二ページ)とミルは説明している。
ただし不正な行為と不道徳な行為とは明確に異なるものである。そのことは不正な行為にたいしては、人々はその行為を遂行した人物を罰する「権利」があるが、慈善を行わないというような道徳に反する行為には、その行為者を罰する権利をもたないことからも明らかである。不正を行った者を罰する権利が人々のうちに生じるかどうかが、たんに非難されるにとどまる不道徳な行為と、処罰すべき不正な行為とを分かつのである。
ミルによって重要なのは、功利の原理がこのような道徳的な感情に沿った形で、社会全体の福利と安全のために役立つ原理であるということである。功利の原理には、社会を構成する個人を保護すべきであるという原理と、社会のうちで生きる人々は共感の原理によって、不正がなされることを許しがたいこと、罰すべきことと考えるものであるという事実があるのである。功利の原理にたいする道徳性の観点からの批判は、人々の享受できる快楽の総量を減らすことがあったとしても、不正を罰し正義を貫く必要があることが多いことを指摘するものであった。ミルはこの批判にたいして、人々は不正をなされた他者に対する共感の感情を抱くものであり、それは社会全体の安全を保護するために役立つものであること、そしてこのような社会の安全の保護こそは、その社会のうちに生きる人々の快楽を最大にする力があるという意味で、功利の原理から当然に帰結するものであることを指摘して、この批判を回避しようとする。
人々が不正を目にして抱く正義の「感情はたんなる憤慨という自然な感情であって、社会的な善の要求と共存することによって道徳的な色合いを帯びたものにすぎない」(二一一ページ)とミルは結論する。このように共感の原理によってミルは功利の思想と正義の感情を結びつけ、それによってこの批判に対処できたと考えるのである。
なお、第4章において意志と欲望が異なるものであるという批判について、ミルは「別のところで述べたように、わたしはこうした見解をほかのどのような人にも劣らず正しいものであるとして強調している」(一三五ページ)と語っていた。この「別のところ」とは、『論理学体系』第六巻第二章第四節「動機は快楽や苦痛を予想したものであるとは限らない」のところである。ここでミルは次のように述べている。
第四節 動機は快楽や苦痛を予想したものであるとは限らない
人間の行為の因果関係についての理論について、多くの人々を悩ませている混乱や誤解を取り除くためには、こうした因果関係には自己形成の力が存在することを認めるだけではなく、さらに別の要因についても考慮する必要がある。というのも意志が動機によって決定されると主張する際に、この動機という言葉によって意味されているのは、必ずしも快楽や苦痛についての予測を意味するのではなく、そのような予測に限られるわけでもないからである。
ここではあらゆる意志的な行為が最初は何らかの快楽を獲得したり、何らかの苦痛を回避したりすることを目指して、意識的に採用される手段にすぎないかどうかという問題については立ち入らないことにしよう。ただし確実なことは私たちは連想の力の影響によって、目的について考えずに手段を望むようになるのは確実だということである。行為そのものが願望の対象となって、その他にどのような動機も考慮せずに行われるのである。(中略)
習慣的になった意志はふつう意図と呼ばれる。わたしたちの意欲の原因や、このような意欲から行われる行為の原因のうちには、好き嫌いだけではなくこのような意味での意図も含まれていると考えなければならない。わたしたちの意図が、その源泉である快楽や苦痛の感情から独立したものとなった時に初めて、わたしたちには確固とした性格がそなわったと評価されるのである。ノヴァーリスは「性格とは意志が完全に何らかの型にはまったものである」と語っている。このように型にはまった意志というものは安定して揺らぐことがないものである。このような時には快楽と苦痛に対する受動的な感受性は著しく弱まっているか、著しく変化してしまっているのである。
このように意欲の原因は動機であり、動機の原因は自らの願望に対するそれぞれの人に特有な感受性と結びついた形でそれぞれの人にとって望ましい対象と思われるもののことである(*8)。
ミルはこの『論理学体系』の第六巻「道徳科学の論理学」においては、性格学とポリティカル・エソロジーの考察を展開しており、その枠組みで人間の行為の因果関係と幸福の問題も検討しているために、ここに引用したような動機と欲望の関係についても考察していたのである。『論理学体系』という名称にもかかわらず、ミルはこの著作でも、『功利主義』の議論と通底する「人間の本性の科学」の確立を目指していたのである。
なお付録として掲載した「ベンサム論」は、『ロンドン・アンド・ウエストミンスター・レヴュー』誌一八三八年八月号に公表されたものである。この論文ではベンサムの思想的な欠陥についてあけすけに批評しながら、ベンサムから受け継いだ功利主義について、ベンサムと父親のジェームズからの思想的な束縛を断ち切った後のミルの考え方について率直に述べているところが注目される。
ミルは『自伝』においてこの著作について、次のように語っている。「この論文でわたしは、ベンサムの長所は十分認めつつ、彼の哲学のあやまりあるいは欠陥と思う点をいくつか指摘した。この批評の骨子はわたしは今でも完全に正当だと考えるが、あれをあの時期に発表したことが正しかったかどうかには、その後ときに疑問を感じてきた。わたしに折にふれて、ベンサムの哲学は進歩への道具として考えたばあい、そのなすべき役割をはたさないうちにある程度世の不信用を買ってしまったように感じられ、そうするとその成果を下げるように一役買ったということは、社会の進歩に貢献するよりもむしろ害を与えることであったたように思えるのである(*9)」。
ミルはこのように、「ベンサム論」ではベンサムの思想の欠陥としてとくに、歴史性や国民性を無視していることを指摘しているが、こうした批判を補うかのよう「功利主義」の論文では、ミルの思想を喧伝することに重点を置いていたのだった。そのことはミルがつづけて、「一方では私自身がベンサムの哲学の根本原理の弁護論を書いて埋め合わせてしている(*10)」と語るとおりである。この二つの論文は、ミルからみたベンサムの思想の欠陥と長所を明確に示すことに役立っているのであり、そこから逆に『自由論』や『論理学体系』などのミル自身の思想を裏側から照らし出す重要な役割を果たしているのである。
なお本書の刊行にあたっては、いつもながら日経BPの黒沢正俊さんにいろいろとご配慮いただいた。記して感謝したい。
二〇二三年秋 中山 元
*2 同、六五ページ。
*3 ベンサム『道徳および立法の諸原理』(中山元訳、ちくま学芸文庫、上巻、二七ページ)。
*4 同、二八ページ。
*5 ミル『自由論』塩尻公明・木村健康訳、岩波文庫、一三五ページ。
*6 同、三〇ページ。
*7 同。
*8 TheCollected WorksofJohnStuartMill,VolumeVIII-ASystemofLogicPartII,Routledge,1974,pp.842-843.
*9 『ミル自伝』前掲書、一九〇ページ。
*10 同。